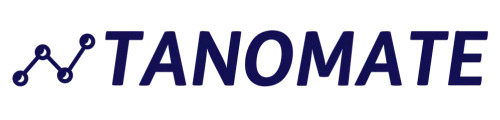教育機関への営業の壁を突破!アポ代行でスムーズに商談へ
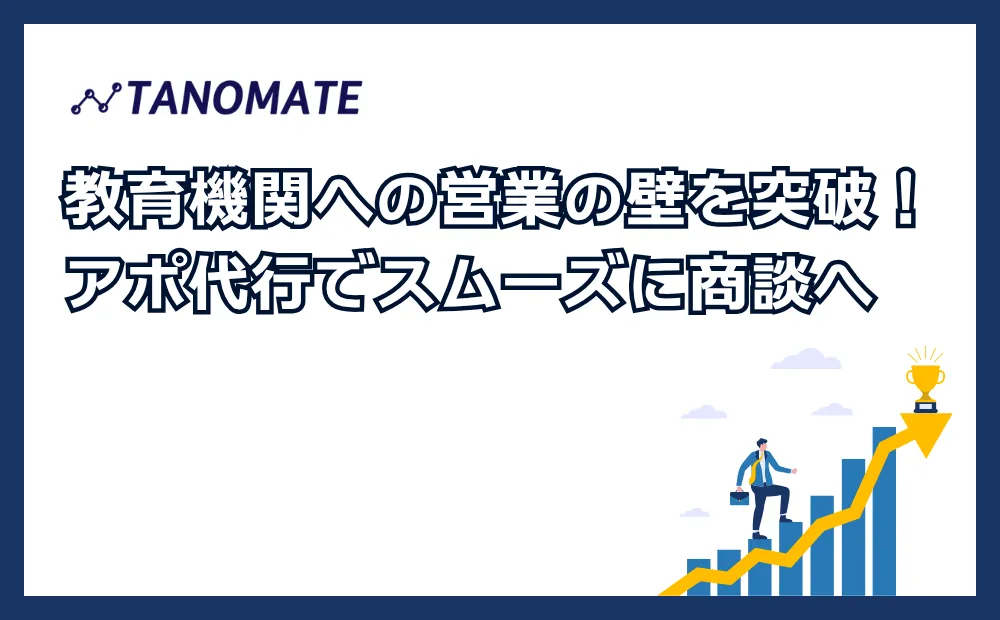
- 1. 教育機関営業で立ちはだかる“3つの構造的な壁”
- 1.1. 電話が通じない・受付ブロックが強い
- 1.2. 誰に話すべきかが読めない、複雑な決裁構造
- 1.3. 校務・行事・予算の“タイミングの壁”
- 1.4. 営業力ではなく、“接点設計力”が試される領域
- 2. 成果が出る営業チームは“初回接点”の質が違う
- 2.1. 成果が出る営業チームは“初回接点”の質が違う
- 2.2. 「話せる状態」を意図的に設計しているか?
- 2.3. 教育現場に響くトーク要素は「サービス説明」ではない
- 2.4. 校種・役職ごとのルート設計ができているか?
- 2.5. 接点の質を高めれば、商談数は必ず伸びる
- 3. アポ代行で突破する“最初の壁”:商談につながる設計とは
- 3.1. 数を追うアポ代行では、教育機関に届かない
- 3.2. 教育業界に特化したアポ代行の3つの強み
- 3.3. アポ+ヒアリング=提案の質を支える情報資産に
- 3.4. “最初の壁”を突破できる設計型アポ代行をパートナーに
- 4. アポ代行活用で“提案に集中できる”体制づくりへ
- 4.1. アポ取得は“プロに任せる領域”という発想
- 4.2. “外注”ではなく“チームの一員”としてアポ代行を活かす
- 4.3. 属人化から“再現できる営業体制”へ
- 4.4. 提案力を活かすために、“接点創出”を切り出そう
- 5. “決裁者に届く営業”を実現するためのチェックリスト
- 5.1. アプローチ先の役職と校内構造を見極めているか?
- 5.2. アポトークに“教育現場への敬意”が込められているか?
- 5.3. 架電タイミングと学校の年間サイクルを把握しているか?
- 5.4. 商談に直結する“現場情報”を取得・共有しているか?
- 5.5. タノメイトは“届く接点設計”に特化したアポ代行
- 6. まとめ
- 6.1. “提案が届く営業”は、設計次第で実現できる

目次
教育機関営業で立ちはだかる“3つの構造的な壁”
「学校法人営業は難しい」と言われる背景には、営業担当者の努力やトークスキルではどうにもならない“構造的な壁”が存在しています。ここでは、教育機関向けに商材やサービスを展開している企業が、新規開拓・商談数獲得で直面しがちな3つの課題について、具体的に整理します。
電話が通じない・受付ブロックが強い
最初の壁は「電話がつながらない」ことです。教育機関は、企業と違い営業窓口という概念がなく、外部からの連絡は基本的に“遮断される”前提で動いています。
特に代表番号に電話をかけると、最初に対応するのは事務職員や守衛の方であるケースが多く、「営業です」と名乗った時点で「担当は不在です」「今は授業中です」「メールでお願いします」といった対応でブロックされてしまうのが実情です。
また、教員は1日の大半を授業や会議、校務処理に充てているため、電話がつながったとしても「今、少しよろしいですか?」と切り出しても、「また改めて」「校務で忙しくて」と断られるケースが後を絶ちません。
誰に話すべきかが読めない、複雑な決裁構造
教育機関には、いわゆる「購買担当」や「意思決定者」が明確に存在しないケースが多く、営業活動の難易度を高めています。
たとえば、ある学校でICT教材の導入を提案する場合、現場では教務主任が実質的に導入の是非を判断していることもあれば、最終的な決裁は校長、あるいは法人の理事会で行われることもあります。学校によっては、教育委員会の許可が必要なこともあり、単独校の判断では動けないということも。
一方、キャリア教育や生徒指導に関するツールでは、進路指導部や生徒指導主任が“影響力のある窓口”になる場合もあります。
このように、学校ごとに異なる決裁ルートを読み解く力が求められます。
校務・行事・予算の“タイミングの壁”
教育機関には、明確に「動けない時期」が存在します。営業の話をしようにも、学校行事や定期試験、入試準備といった業務が優先されるため、営業の優先順位はどうしても後回しになります。
たとえば、以下のような“タイミングNGゾーン”があります:
3月:卒業式・教員の異動準備で多忙、対応困難
6〜7月:期末テストや保護者面談が集中し、校内はバタバタ
1〜2月:受験や進路指導で、提案の時間を確保しづらい
また、予算確保の都合で「良い提案だけど、今年度は予算がない」という理由で見送りになることも少なくありません。
このように、“予算と年度スケジュール”の制約が、商談化を阻む大きな要因となっています。
営業力ではなく、“接点設計力”が試される領域
教育機関 営業では、「つながらない」「会えない」「今は無理」と言われるのが“当たり前”の世界です。だからこそ、従来の法人営業とは違うロジックで、学校法人決裁者との“初回接点”をどうつくるかが成果の分かれ目になります。
次章では、こうした制約を乗り越えて成果を出している営業チームが実践している「初回接点の設計手法」について、具体的に解説していきます。
成果が出る営業チームは“初回接点”の質が違う
教育機関 営業では、「つながらない」「会えない」「今は無理」と言われるのが“当たり前”の世界です。だからこそ、従来の法人営業とは違うロジックで、学校法人決裁者との“初回接点”をどうつくるかが成果の分かれ目になります。
次章では、こうした制約を乗り越えて成果を出している営業チームが実践している「初回接点の設計手法」について、具体的に解説していきます。
成果が出る営業チームは“初回接点”の質が違う
教育機関への営業で成果を出している企業に共通しているのは、単に「アポが取れた」ではなく、「話せる状態をつくること」に成功している点です。電話がつながりにくい、決裁者が見えない、タイミングが合わない——そんな壁を超えるには、“初回接点”の質そのものを上げる設計が必要不可欠です。
「話せる状態」を意図的に設計しているか?
アポ取得がゴールになってしまうと、実際の商談化率は上がりません。
逆に成果を上げている営業チームは、「この相手となら、今、こういう話ができる」という設計を持ってアプローチしています。
たとえば、ICT教材を扱う企業であれば、ターゲットとなるのは情報主任や教務主任。その上で、教頭・校長へと話が展開するルートを見越し、初回接点では「現場課題のヒアリング」に徹するケースも少なくありません。
つまり、“誰に・いつ・何を・どう伝えるか”まで明文化された設計が、成果を分ける大きな要因になっているのです。
教育現場に響くトーク要素は「サービス説明」ではない
教育機関の営業では、サービスの機能やスペックを訴求するだけでは響きません。成果を出している営業チームは、初回接点の段階で「現場が抱える課題」に応じたトーク構成を意識しています。
特に有効なのは、次の3要素です:
・教育効果
「児童・生徒の理解が深まる」「キャリア形成に役立つ」など、“子どもにとってどうか”を中心に据えることで、現場の先生の共感を得やすくなります。
・業務軽減
「授業準備の時間が短縮される」「校務が効率化される」など、教員の働き方改革を後押しする視点も有効です。
・他校事例
「同エリアの中学3校で導入済み」「教育委員会でも採用実績あり」など、横並び意識の強い学校現場では、近隣の成功事例が安心材料になります。
これらのトーク要素を、相手の役割や関心に合わせて提示できているかどうかが、“聞いてもらえるアポ”か、“ただの営業電話”かを分ける決定的な要因になります。
校種・役職ごとのルート設計ができているか?
営業成果が出ているチームは、校種ごと・役職ごとの意思決定プロセスを分析し、段階的なアプローチ設計をしています。
たとえば:
・ICT教材(中高)
教務主任 → 教頭 → 校長
・進路支援ツール(高校)
進路指導主事 → 教頭 → 校長 or 法人理事
・保護者対応DX(小学校)
事務主任 → 校長 → 教育委員会との協議
このように、最初に誰を押さえ、次に誰に伝えてもらうかという“ルート設計”を意識している企業は、商談への移行スピードが格段に違います。
接点の質を高めれば、商談数は必ず伸びる
教育機関 商談数を増やすには、アポ件数の量ではなく、「この接点は話ができる状態か」という質の高い初回接点を設計できているかが勝負どころです。そしてこの“入口の精度”を高めることは、営業の時間投資効率を最大化する鍵にもなります。
次章では、その“初回接点”の精度を支える手段として、アポ代行 教育業界での活用方法と、その具体的な支援体制について解説していきます。
アポ代行で突破する“最初の壁”:商談につながる設計とは
教育機関 営業において最大のボトルネックは、「そもそも話せる場を作れないこと」にあります。アポがなければ、提案は届かない。だからこそ、“初回接点”の質が、営業成果の8割を左右すると言っても過言ではありません。
この初回接点を外部に委ねる手段として「アポ代行」がありますが、件数だけを追う“電話数重視型”では教育機関には通用しません。 成果を出すには、業界特性に即した“設計型”のアポ代行を選ぶことが不可欠です。
数を追うアポ代行では、教育機関に届かない
一見すると、アポ代行は「アポ件数を確保するサービス」と思われがちです。
しかし、教育機関 新規開拓の現場では、量よりも“接点の質”が圧倒的に重要です。
たとえば、忙しい教員に突然営業電話をしても、「今、授業中なので…」「担当が分からないので…」と断られるのが常。件数を稼ぐだけの架電では、担当者にも、ましてや決裁者にもたどり着けません。
教育業界に特化したアポ代行の3つの強み
成果につながるアポ取得のために、タノメイトのような教育機関に強みを持つアポ代行では、以下の3点を徹底しています。
① 教育的配慮のある話法・言葉選び
「先生方のご負担にならない範囲で」「子どもたちの成長支援につながる内容です」といった、学校文化にフィットした話し方が基本です。営業色を出しすぎると、即座に拒否反応が出るため、“説明”ではなく“対話のきっかけ”をつくる言葉選びが鍵となります。
② 架電時間帯・季節に応じた設計
教育機関には、架電してはいけないタイミングがあります。たとえば3月の卒業式前、6月の期末テスト前後、9月の文化祭シーズンなど、校内が多忙を極める時期はアプローチNGです。
タノメイトでは、月別・校種別の“静かな時間帯”を把握し、アプローチスケジュールを調整しています。
③ 決裁フローを読んだターゲティング
校種(小・中・高・大学)や設置主体(公立/私立)によって、誰が意思決定に関わるかは大きく異なります。
たとえば、私立高校なら法人事務局、大学なら学部長、公立小中なら教頭・校長といったように、架電前から“決裁ラインを読み切ったターゲット選定”ができているかがポイントです。
アポ+ヒアリング=提案の質を支える情報資産に
タノメイトでは、アポ取得だけでなく、その過程で得られる現場の反応・ニーズ・導入時期などのヒアリング内容をレポート化し、営業チームにフィードバックしています。この情報によって、提案資料のチューニングやプレゼンの切り口が具体化され、“会えば決まる”商談への質的支援が可能になります。
“最初の壁”を突破できる設計型アポ代行をパートナーに
教育機関営業の成果を分けるのは、「アポが取れるか」ではなく、「商談につながる接点をつくれるか」です。
件数重視のアポ代行ではなく、“学校現場を理解した設計型パートナー”と連携することが、結果として営業全体のパフォーマンスを底上げします。
次章では、こうしたアポ代行をどう営業戦略に組み込むか、商談数を安定化させる“外部連携型の営業体制”について解説していきます。
アポ代行活用で“提案に集中できる”体制づくりへ
教育機関への営業活動では、営業担当者が「提案に行きたくても、そもそもアポが取れない」という課題に直面しがちです。特に少人数体制で動いている企業では、架電・商談・資料作成・社内会議まで一人で抱えるケースも珍しくありません。結果として、最も時間をかけるべき提案活動が後回しになるという“営業の空回り”が起きています。
アポ取得は“プロに任せる領域”という発想
実際に、教育機関向けの営業で成果を出している企業ほど、アポ取得フェーズを戦略的にアウトソースしています。あるICT教材提供企業では、営業メンバー5名のうち3名が新規アポ取得に稼働していた状態から、アポ代行導入によって商談数を維持しながら1名での新規対応に切り替え、他のメンバーは既存校への提案・クロージングに集中する体制を構築。結果として受注率が上昇し、営業の回転率が向上しました。
教育機関 アポ取り方に悩むチームこそ、初回接点を“自社の営業メンバーが担うべき業務なのか?”という視点で見直すべきです。
“外注”ではなく“チームの一員”としてアポ代行を活かす
営業支援 教育機関に特化したアポ代行は、ただのテレアポ業者ではありません。たとえばタノメイトは、導入企業と共に営業フローを設計し、「どの校種の、どの役職に、どのようにアプローチするか」を事前に戦略立ててから稼働します。
具体的には:
「私立中学は教頭が現場判断するケースが多い」
「公立高校では、まず進路指導部の了承を得てから校長へ話を上げるのがスムーズ」
「7月下旬はテスト後で時間が取りやすいが、9月以降は行事で多忙になる」
と言った学校法人に対してのアプローチに必要な“現場情報”を織り込んだスクリプトやタイミング設計を提案し、営業と一体で動きます。
属人化から“再現できる営業体制”へ
営業現場でよくあるのが、「〇〇さんがいればアポが取れる」という属人的な状態。しかし、それでは異動や退職で営業活動が一気にストップしてしまいます。
アポ代行を活用すれば、「このリストに、この時間、このトークでアプローチすれば、この確率で商談化する」というデータが蓄積されていきます。この営業設計の“再現性”こそが、商談数を安定的に確保する土台となるのです。
タノメイトでは、アポ獲得後のレポートに現場ヒアリングを添えることで、提案内容の微調整まで可能な状態に整備しています。営業担当はその情報をもとに、“行けば決まる状態”をつくってから訪問できる──これが、属人化を超えた営業組織のあり方です。
提案力を活かすために、“接点創出”を切り出そう
教育機関 商談数を安定的に積み上げるには、営業担当が「一から電話し、関係をつくり、提案までこなす」スタイルを手放す必要があります。
アポ代行 教育業界に強いパートナーと連携することで、提案・クロージングという営業の本質的価値に、リソースを集中できる体制を築くことができます。
次章では、そのような営業体制を実現するために、どのようなアポ代行を選ぶべきか──成果につながるアポ代行 選び方の具体的な視点を解説します。
“決裁者に届く営業”を実現するためのチェックリスト
「教育機関への営業がうまくいかない」と感じる担当者の多くが抱える共通課題――それは、「決裁者に届いていない」ことです。どれだけ商材が優れていても、提案先が間違っていたり、タイミングを誤ったりすれば、商談に至ることはありません。
ここでは、教育機関向けの営業で確実に“商談に届く”ために必要な実践的チェックポイントを具体的に整理します。
アプローチ先の役職と校内構造を見極めているか?
営業で最も重要なのは、“誰に話すか”の精度です。
例:
・ICT教材の場合:教務主任 → 教頭 → 校長
・キャリア支援ツールの場合:進路指導主事 → 教頭 → 校長
・学校運営支援(DX)サービスの場合:事務主任 → 教頭または事務長 → 校長/理事会
校種やエリアによっても意思決定フローは異なります。
ポイント:
担当者に「私が判断できない」と言われる前に、“次に誰に話を通すのか”を先回りして確認・準備しておくことが極めて重要です。
アポトークに“教育現場への敬意”が込められているか?
「営業の電話です」と切り出した瞬間、話が終わってしまうのが教育機関営業のリアルです。
商談に進める営業担当者ほど、初回トークの中でこうした表現を自然に取り入れています。
例:
「先生方のご負担を少しでも減らせるご提案でして…」
「近隣校で好評いただいている導入事例があり…」
「生徒の学習意欲に変化があったという声も多く…」
ポイント:
“売り込む”のではなく、“相談される”立ち位置を意識し、教育効果や他校導入事例を引き合いに出すことで、話を聞く理由を作ります。
架電タイミングと学校の年間サイクルを把握しているか?
教育機関は時間の流れが特殊です。営業の都合では動いてくれません。
避けたい時期の一例:
・2〜3月:卒業式/教職員の人事異動準備
・6月/11月:定期試験・進路三者面談などが集中
・9〜10月:文化祭や公開授業の準備期間
逆に、5月・7月・11月後半〜12月など、比較的余裕がある時期に絞って接触することで、対応率が上がります。
ポイント:
学校ごとの行事予定を事前にリサーチし、「このタイミングでこの役職に話せるか」のカレンダー管理を営業設計に組み込みましょう。
商談に直結する“現場情報”を取得・共有しているか?
初回接点で得られた情報は、提案の質を左右します。タノメイトでは、以下のような情報をアポ取得時にヒアリングし、営業チームにレポートしています。
例:
「ICT予算はすでに法人本部で確保済み」
「昨年度タブレット導入済だが教材面で課題あり」
「今の学年主任が“新しい教材に前向き”」
ポイント:
アポを取るだけで終わりにせず、提案に必要な文脈を拾い、営業チームと共有する体制を整えることが、商談化率を引き上げる鍵です。
タノメイトは“届く接点設計”に特化したアポ代行
こうしたチェックリストを満たすアポ取得を、すべて自社内で実現するのは容易ではありません。教育機関に特化したアポ代行サービス「タノメイト」は、学校法人 決裁者との“話せる接点”を戦略的に設計・実行し、貴社の営業活動の最前線を支援します。
営業が“提案に集中できる”状態をつくるために、初回接点のプロに任せるという選択肢を、ぜひご検討ください。
まとめ
“提案が届く営業”は、設計次第で実現できる
どれだけ魅力的なサービスでも、教育機関の決裁者に届かなければ営業は始まりません。現場では、「話せれば分かってもらえるのに、アポが取れない」「決裁ルートが見えない」という声が後を絶ちません。
タノメイトは、教育機関営業に強みを持つ“初回接点のプロ”として、アポ取得から情報共有までを徹底サポート。
商談数を安定化させたい、営業を仕組み化したい——そんな貴社の外部パートナーとして並走します。
教育機関 新規開拓・学校法人 決裁者へのアプローチにお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
👉 ご相談はこちらから|教育機関 アポ取り方を見直す最初の一歩を。

タノメイト編集部です。テレアポのプロの視点から、テレアポに関するさまざまな情報をわかりやすく発信します。
【タノメイトとは?】
タノメイトは「質の高いリード獲得」にこだわる、成果報酬型テレアポ代行サービスです。リード獲得にお悩みの企業様はぜひお問い合わせください。
商談につながるアポを獲得
完全成果報酬型テレアポ代行
『タノメイト』
● 初期費用・固定費0円
リードを獲得した分だけお支払い。完全成果報酬型でリスクゼロだから今すぐ始められます。
● 質の高いリード獲得
成功事例に基づくスクリプトと精度の高いリストを活用。質の高いリードを獲得します。
● 安心のキャンセル保証
条件をクリアしたリードのみご案内。条件を満たさないリードはキャンセル可能です。

\ リスクゼロで始めるテレアポ代行 /