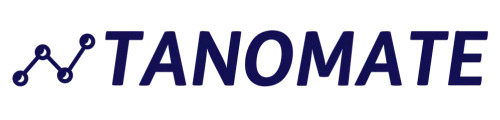教育業界の商談数を増やす!学校法人に響くアプローチの作り方
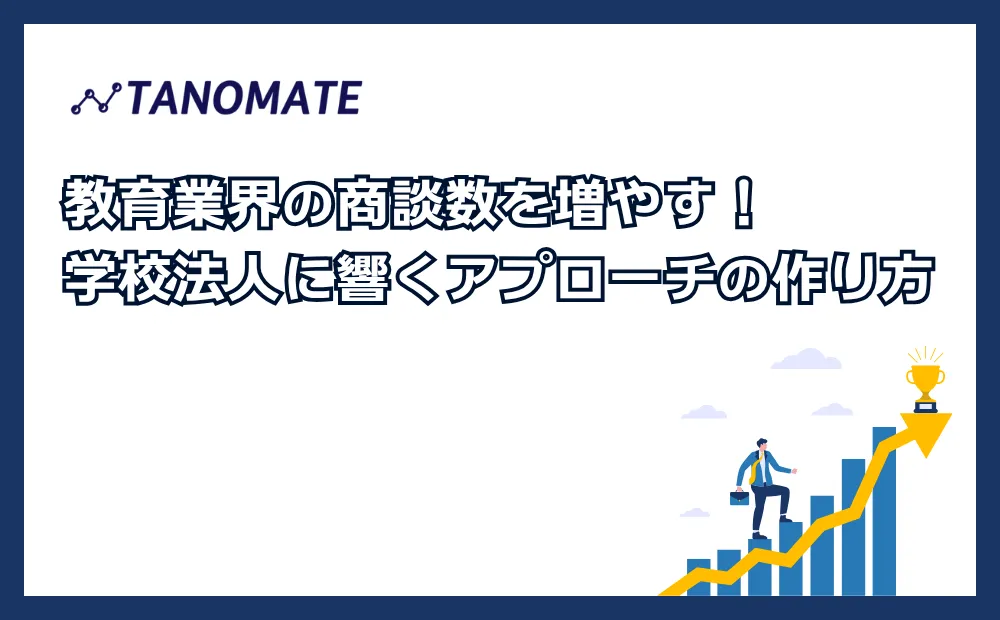
教育機関への営業で、「提案内容には自信があるのに商談につながらない」と感じていませんか?
学校法人は、教育的配慮・決裁フロー・タイミングの壁など、一般企業とは異なるアプローチが求められます。
実際、多くの営業現場で成果が伸び悩むのは、営業スキルではなく“接点の設計”に問題があるケースがほとんどです。
本コラムでは、「教育機関営業で商談数を増やす」ためのアプローチ設計について、学校法人決裁者との初回接点をどうつくるかを軸に、具体的な戦略とアポ代行の活用法を解説します。
- 1. なぜ教育機関は“商談につながりにくい”のか
- 1.1. 教育機関は「営業を前提としていない組織」
- 1.2. 誰が決裁者なのか“読み切れない”組織構造
- 1.3. 予算サイクルと行事カレンダーの“タイミングの壁”
- 2. 教育機関営業で商談につながる“入口設計”の条件
- 2.1. 「アポ取得=成果」ではない教育機関営業
- 2.2. 初回接点で心を動かす“3つのキーワード”
- 2.3. 接点設計に必要な“情報と順番”
- 2.4. 「接点設計」は教育営業における戦略の要
- 3. “営業が空回りする会社”が見落としている設計ミス
- 3.1. 設計ミス①:架電リストに「誰と話すか」が設計されていない
- 3.2. 設計ミス②:トーク内容が「自社サービスの説明」に終始している
- 3.3. 設計ミス③:アプローチタイミングが“営業都合”で決められている
- 3.4. 設計ミス④:決裁者でなく“情報収集者”に粘り続けている
- 4. タノメイトが支援する“商談につながるアポ取得”の考え方
- 4.1. 教育機関に本当に“届く”アプローチとは?
- 4.2. 実際の支援イメージ
- 4.3. 「質の高い初回接点」が教育機関営業の未来を変える
- 5. 商談数を安定化させる“外部連携型の営業設計”とは
- 5.1. 提案・クロージングに集中するための“入口の分業化”
- 5.2. 属人的な営業から“再現性のある設計”へ
- 5.3. 外注先ではなく、“営業チームの一員”として並走できるか
- 5.4. “入口の仕組み化”が、営業成果を加速させる
- 6. まとめ
- 6.1. “通じる営業”は、質の高い初回接点から生まれる

目次
なぜ教育機関は“商談につながりにくい”のか
「教育機関への提案は、内容が悪いから通らないのではない」
これは、多くの教育業界向け営業担当者が感じている共通の実感です。実際、提案内容に手応えを感じていても、「先生に会えない」「話せない」「たどり着かない」といった“接点の壁”によって、商談以前の段階でストップしてしまうケースが多発しています。
教育機関は「営業を前提としていない組織」
企業営業では、窓口担当や役職名から比較的容易にキーパーソンを特定できますが、教育機関営業はその前提が通用しません。
まず、学校法人は営業活動を“受け入れる文化”を持っていないという点が大きな違いです。
電話の一次対応は多くが事務職員や教頭であり、営業電話と分かった瞬間に遮断されるケースが一般的。いわゆる“電話ブロック”が極めて強固な領域です。
また、現場の教員は授業・校務・生徒対応に追われ、日中の時間帯に外部の営業とじっくり話す余裕はまずありません。
アポイントなしに訪問しても、授業中・会議中で取り次ぎ不可のことが多く、「本当に必要な提案であっても、“話す場”がそもそもつくれない」構造になっています。
誰が決裁者なのか“読み切れない”組織構造
教育機関営業で頻繁に聞かれるのが、「誰に話せばいいかわからない」という悩みです。
たとえば、ICT教材や学校向けアプリを提案する際、
・校長が最終的な決裁者なのか
・教務主任が現場推進のキーパーソンなのか
・それとも教育委員会が予算承認の権限を持つのか
といった判断が、校種・地域・運営法人によってバラバラです。
さらに、私立学校では理事長や法人事務局が鍵を握ることもあり、“肩書き=決裁者”ではないという構造的な複雑さがあります。このため、営業活動がどこを起点に、どのルートで展開されるべきかが非常に読みにくく、アプローチの精度が成果に大きく影響します。
予算サイクルと行事カレンダーの“タイミングの壁”
教育機関のもうひとつの難しさは、営業のタイミングが限られていることです。
企業であれば年度内で随時導入検討が進むこともありますが、学校では「予算確定」「年度替わり」「長期休暇」「行事」など、商談に適した時期が明確に限られます。
たとえば:
・4〜6月は新学期対応で多忙、提案どころではない
・夏休み期間中は学校に人がいない
・10〜11月は来年度予算検討のチャンス
・1〜2月は受験・卒業対応で連絡がつきにくい
このように、「いつ・誰に・どの順で話をすればいいか」が複雑で、タイミングを誤れば、たとえニーズがあっても“見送られる”リスクが極めて高いのが教育機関営業の現実です。
◆教育機関の営業は、内容より“接点の作り方”が9割
「話せれば通る商材なのに、商談が生まれない」。
この背景には、教育機関が持つ構造的な営業障壁が横たわっています。
本コラムでは、この“話せない壁”を突破し、商談数を着実に増やしていくためのアプローチ設計とアポ代行の活用法を、次章以降で具体的に掘り下げていきます。
教育機関営業で商談につながる“入口設計”の条件
教育機関向けの営業において、「アポが取れても商談につながらない」「提案まで漕ぎつけられない」という声は少なくありません。その原因は、提案内容ではなく、“入口の設計”にこそあります。ただ通電して話すのではなく、「相手が話を聞く準備ができている状態=話せる接点」をどう設計するかが、商談数の鍵を握ります。
「アポ取得=成果」ではない教育機関営業
企業営業では、アポ=ヒアリング・提案の起点と捉えられがちですが、教育機関ではアポ自体が「形だけ」で終わることもあります。
理由は明確で、教育現場では“営業の場”が前提として存在しないからです。先生方は限られた時間のなかで授業・校務・保護者対応に追われ、営業の話を聞く余裕がありません。
したがって、教育機関では「アポを取る」こと以上に、“話せる状態をどう作るか”の設計=入口の質が重要です。
初回接点で心を動かす“3つのキーワード”
教育機関に刺さるトークは、製品・サービスの機能ではなく、「現場目線での価値」に落とし込まれているかどうかで反応が大きく変わります。具体的には、次の3点が初回接点の突破口になります。
①教育効果(=子どもにとって良いか)
例:「学力が伸びる」「非認知能力が育つ」「進路選択の幅が広がる」など、児童・生徒へのベネフィットは、どの校種でも響く強力な要素です。
②教職員の業務軽減
「教材準備の時間が減る」「学級経営の負担が軽くなる」「保護者対応がスムーズに」など、現場のリアルな課題を解消できる切り口は、特に管理職層に刺さります。
③他校での導入実績
「同エリアの中学校3校で導入済み」「A区の教育委員会でも採用」など、近隣・同規模の学校事例は、共感と信頼の下地になります。教育現場は横並びを重視する傾向が強いため、地縁・校種・課題別の事例整理は不可欠です
接点設計に必要な“情報と順番”
商談につながるアポを作るには、誰に・いつ・どうアプローチするかを“事前に読み切る”ことが求められます。具体的には以下の情報整理が必要です。
・校種と設置主体(公立/私立/専門学校/法人本部)
・役職別の機能理解(教務主任:現場推進/教頭:中間管理/校長:決裁者)
・稟議ルートの予測(現場起点か、法人起点か)
・検討スケジュール(導入時期・補助金有無・年度予算との整合)
これらをふまえたうえで、誰から接点を取るかの「接触順序」が決まります。

このように、最初から“校長を狙う”のではなく、合意形成の段階を踏むことで、提案を通す“土台”が築かれます。
「接点設計」は教育営業における戦略の要
教育機関営業は、提案力よりも入口戦略=誰に・何を・どのタイミングで伝えるかの設計が命です。この戦略設計が弱いと、アポは取れても手応えがない、商談にはならない、という“空回り”が続きます。
逆にこの入口設計がしっかりできている営業チームは、少ないアプローチ数でも高い商談率と成果を出しています。
次章では、商談数が伸び悩む企業が見落としている“設計ミス”について掘り下げていきます。
“営業が空回りする会社”が見落としている設計ミス
教育機関営業において、「アポは取れているのに商談に進まない」「手応えはあるのに受注につながらない」といった“営業の空回り”が起きるケースは珍しくありません。その多くは、現場の努力や商材力ではなく、営業設計のミスが原因です。ここでは、商談数が伸び悩む企業に共通する4つの設計ミスについて整理します。
設計ミス①:架電リストに「誰と話すか」が設計されていない
多くの営業チームが「学校一覧」や「担当不明リスト」に頼ったまま架電をスタートしてしまいます。
しかし、教育機関では“誰に話すか”を間違えると、その先が一切進まないという特徴があります。
たとえば、ICT教材の提案を理事長にいきなりかけても「現場が決めるから」と返されるケースは珍しくありません。一方で、教務主任にアプローチした結果、校長を巻き込んで商談が進むこともあります。
架電リストの段階で、役職・部門・決裁ルートを読み込んだ設計ができていないと、結果として“誰にも届かない営業”に陥ります。
設計ミス②:トーク内容が「自社サービスの説明」に終始している
「サービスの機能や特徴は十分伝えたはずなのに、興味を持ってもらえない」
これは、“教育の現場目線”を欠いたトークによって、初回接点が無意味な時間になっている典型例です。
教育機関の担当者が求めているのは、「それが自校にとってどう役立つか」という視点です。
・「子どもの学びにどう寄与するのか」
・「現場の負担がどう減るのか」
・「他校ではどう使われているのか」
このような教育機関特有の関心ごとを無視し、自社目線の“カタログ説明”を続けていては、心は動きません。
設計ミス③:アプローチタイミングが“営業都合”で決められている
教育機関には、明確な「話が進みやすい時期」と「完全に避けるべき時期」が存在します。にもかかわらず、「営業目標があるから今月中に」「キャンペーン中だから早く動きたい」といった営業都合でのアプローチが、商談機会を自らつぶしてしまっているケースは少なくありません。
例えば:
・3月:卒業・人事異動対応で教職員が最も多忙。営業アプローチは極力NG。
・6月〜7月:期末試験と面談時期が重なる。提案は一時保留になりやすい。
・10月:次年度予算策定前の“提案のチャンス”。ここを逃すと次年度まで動かないことも。
タイミングを読み誤ることで、「せっかくの提案」が“今は無理です”の一言で流れてしまいます。
設計ミス④:決裁者でなく“情報収集者”に粘り続けている
営業の現場では、対応が丁寧な教員や事務職員に“可能性”を感じてしまい、そのまま何度も接触を重ねてしまうというケースがよくあります。
しかし、その相手に決裁権限や影響力がなければ、どれだけ接点を重ねても商談にはつながりません。
とくに教育機関では、「現場の声は大事にするが、最終判断は別の人」という構造が一般的です。現場ヒアリングで得た情報を鵜呑みにしても、稟議のステップを読み間違えれば、提案書すら見られずに終わることもあります。
設計=成果。営業設計の“ズレ”は、必ず数字に表れる
商材に自信があるのに、なぜか商談数が増えない。それは、営業のやり方が間違っているのではなく、“誰に、いつ、どう話すか”の設計がズレているからです。
裏を返せば、このズレを見直し、教育機関に特化したアプローチ設計を徹底することで、商談数も受注率も着実に上がります。
次章では、こうした設計を効率的に実行する手段として注目される「アポ代行」の活用法について、具体的に解説していきます。
タノメイトが支援する“商談につながるアポ取得”の考え方
教育機関営業におけるアポイント取得の目的は、「数」ではなく「成果」です。
いかに多くのアポを獲得しても、それが提案や商談につながらなければ意味がありません。
私たちタノメイトは、“会えば決まる相手”に確実につながる初回接点の設計・実行に特化したアポ代行サービスとして、教育業界における商談創出を支援しています。
教育機関に本当に“届く”アプローチとは?
教育機関に対するアプローチでは、電話1本、言葉1つの印象が商談成否を左右します。だからこそタノメイトは、「ただ架ける」のではなく、「どう話すか」「誰に話すか」を緻密に設計したアプローチを徹底しています。
特に意識しているのは以下の3点です:
① 教育的配慮のあるトーク設計
・「お忙しい時間帯に失礼いたします」「ご指導の参考になれば幸いです」など、学校文化に馴染む言葉選び
・授業や行事を妨げない架電時間帯(10:30〜11:30、15:00以降など)
・トーク冒頭での“切り出し方”も、「他校導入事例の共有」「〇〇教育委員会の推薦」が有効です
② 決裁構造を踏まえたリスト戦略
校種(小・中・高・大学)や法人(公立・私立)ごとに、実際に意思決定に影響を持つ人物は異なります。
例えば、ICT教材であれば教務主任や情報担当がキーパーソン、キャリア系教材であれば進路指導部からの接点が有効です。
タノメイトでは、役職別・部門別にアプローチルートを設計したうえで、戦略的にリスト化しています。
③ 商談に活きるヒアリングレポート
アポ取得にとどまらず、「どのような反応だったか」「導入検討時期は?」「誰が関心を示したか」といったヒアリング情報を整理してご報告。
営業担当者がその後の提案を組み立てやすいよう、“商談準備の土台”として活用できる状態で情報提供しています。
実際の支援イメージ
たとえば、あるキャリア教育サービスを提供する企業では、アポ代行導入前は「年間20商談・受注率15%」と伸び悩んでいました。
タノメイト導入後、ターゲット校種・地域を絞ったアプローチに切り替え、初回接点の質を強化。
結果、月間アポ獲得数は1.5倍、商談化率は約40%、受注率も倍近くに改善しました。
特筆すべきは、アポ数の増加だけでなく、営業チームから「訪問すれば話が早い」「校内検討がスムーズになった」との声が多く上がった点です。
“ただ会う”のではなく、“会った瞬間に話が進む”接点をつくることが、商談数を確実に引き上げるカギなのです。
「質の高い初回接点」が教育機関営業の未来を変える
教育機関への営業は、地道で繊細なプロセスを必要とします。
タノメイトは、単なるテレアポ代行ではなく、教育業界に特化した“入口づくりのプロフェッショナル”として、御社の商談創出を支えます。
「アポは取れているが、なぜか商談が生まれない」
「現場に響くトークが組み立てられない」
そんな課題を感じている企業様にこそ、“質”を重視したアポ設計と支援が有効です。
次章では、このような仕組みをどのように社内営業戦略と連携させるかを解説していきます。
商談数を安定化させる“外部連携型の営業設計”とは
教育機関との商談を安定的に創出し続けるには、属人的な営業から脱却し、再現性のある仕組みをつくることが欠かせません。
一時的に成果を出すことはできても、メンバーの異動や人手不足で失速してしまうチームは少なくありません。
そこで近年注目されているのが、「アポ取得は外部に任せ、提案とクロージングに集中する」外部連携型の営業設計です。
提案・クロージングに集中するための“入口の分業化”
教育機関営業では、「決裁者にたどり着く」こと自体が難易度の高い仕事です。
校内の組織構造やスケジュールを読み、現場目線のトークを展開し、慎重に接点をつくっていく——。
この“最初の一歩”に多くの時間と労力がかかるのが実情です。
そのため、初回接点の獲得は専門パートナーに任せ、社内営業は商談以降の価値訴求に集中するという分業体制を採る企業が増えています。
この体制に切り替えることで、営業担当者は「本来の強み」であるヒアリングや提案に専念でき、限られたリソースで最大限の成果を上げる土台が整います。
属人的な営業から“再現性のある設計”へ
教育機関営業では、ベテランの属人的ノウハウに頼っているチームも少なくありません。
しかし、「〇〇さんにしか通じないやり方」では、再現も拡張もできません。
そこで重要なのが、営業フローの可視化・標準化です。
具体的には以下のような項目を整理していきます:
・誰に:役職別・校種別ターゲットの明確化
・何を:相手の関心軸に合ったトークのパターン化
・いつ:年間行事・予算サイクルを見据えたタイミングの設計
この情報を整理・共有できれば、新人や他部門メンバーでも一定の成果が出せるようになり、チーム全体で商談数を積み上げられる仕組みへと進化します。
外注先ではなく、“営業チームの一員”として並走できるか
このような営業設計を実現する上で、アポ代行は単なるアウトソース先ではなく、営業戦略の一端を担う“外部メンバー”として機能することが重要です。
私たちタノメイトは、教育機関営業に特化したアポ代行として、単に件数を追うのではなく、「会えば話が進む相手」との質の高い接点を設計・実行します。
・教育現場に配慮したトーク、架電設計
・校種別、役職別のリスト構築と接触順設計
・商談準備に役立つヒアリングレポートの共有
こうした支援を通じて、お客様の営業チームと一体となりながら“成果につながる入口”を創り出します。
“入口の仕組み化”が、営業成果を加速させる
教育機関営業の商談数を安定的に伸ばしていくには、個人に頼らず、チームで営業の成果を再現できる体制づくりが欠かせません。
そしてそのためには、「最初の接点=入口」の質を担保できる外部パートナーとの連携が、極めて有効です。
タノメイトは、教育業界に特化したアポ取得の専門パートナーとして、営業成果の仕組み化を全力でサポートしています。
今後、より戦略的な教育機関営業体制を検討されている企業様は、ぜひ一度ご相談ください。
まとめ
“通じる営業”は、質の高い初回接点から生まれる
教育機関への営業で成果を上げるには、「話せば伝わる」ではなく「話せる状態をどう設計するか」が鍵になります。
タノメイトは、教育機関に特化した“初回接点創出”のプロとして、会えば決まる相手との接点づくりを支援しています。
「商談数を増やしたい」「営業を仕組み化したい」とお考えの方は、ぜひ一度サービスページをご覧ください。
👉 詳しくはこちら ▶ https://tanomate.net/

タノメイト編集部です。テレアポのプロの視点から、テレアポに関するさまざまな情報をわかりやすく発信します。
【タノメイトとは?】
タノメイトは「質の高いリード獲得」にこだわる、成果報酬型テレアポ代行サービスです。リード獲得にお悩みの企業様はぜひお問い合わせください。
商談につながるアポを獲得
完全成果報酬型テレアポ代行
『タノメイト』
● 初期費用・固定費0円
リードを獲得した分だけお支払い。完全成果報酬型でリスクゼロだから今すぐ始められます。
● 質の高いリード獲得
成功事例に基づくスクリプトと精度の高いリストを活用。質の高いリードを獲得します。
● 安心のキャンセル保証
条件をクリアしたリードのみご案内。条件を満たさないリードはキャンセル可能です。

\ リスクゼロで始めるテレアポ代行 /