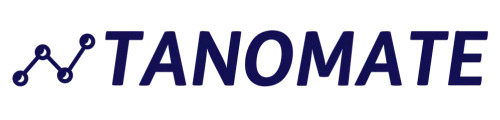「休眠顧客が商談化する!」成果につながる掘り起こしアプローチとは?
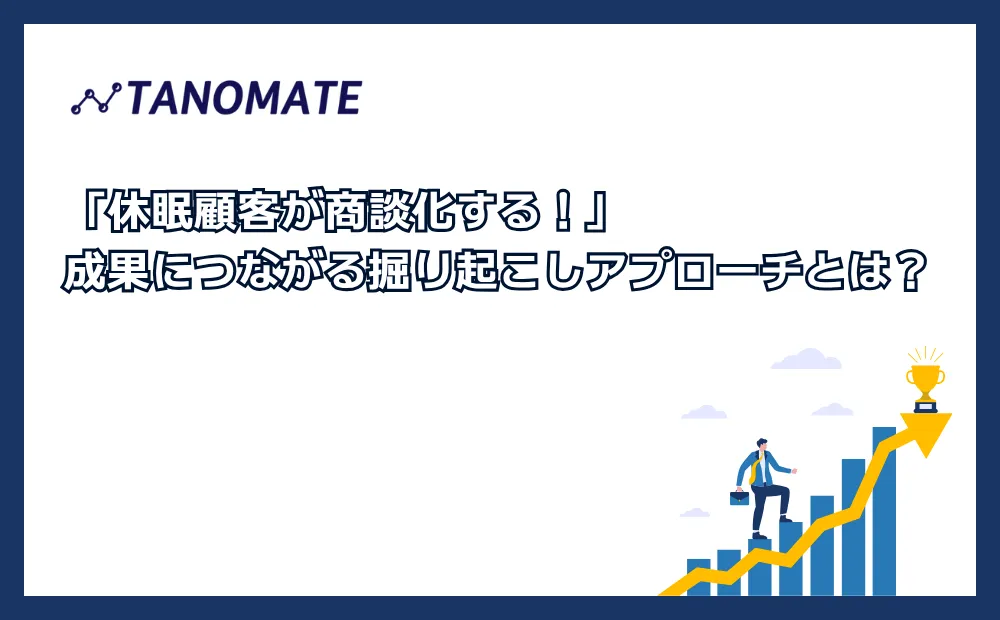
「以前は良い関係だったのに、連絡が取れない」「案内しても反応が薄い」——そんな“休眠顧客”に悩んでいませんか?
実は休眠顧客は、新規よりも受注確度が高く、再接点さえ作れれば大きな商談チャンスにつながります。
しかし、過去のつながりだけでは響かないのも事実。必要なのは、「接点を再設計する営業戦略」です。
本コラムでは、BtoB営業における休眠顧客掘り起こしの最適なアプローチと、成果を生むテレアポの活用術について具体的に解説します。
- 1. なぜ休眠顧客は“難しく”見えるのか?
- 1.1. なぜ、休眠顧客が“難しく”見えるのか?
- 1.2. 再接点を作るきっかけが重要
- 1.3. 営業現場での勘違いに注意
- 1.4. キーワードを活かした営業戦略へ
- 2. 掘り起こし成功企業の共通点とは?
- 2.1. 顧客を再評価する:過去ではなく現在に注目する
- 2.2. 掘り起こしの切り口を分ける:休眠理由に合わせたアプローチ
- 2.3. 休眠理由別のアプローチ方法
- 2.4. CRM・SFAツールを活用した掘り起こし戦略
- 2.5. 掘り起こし戦略の本質:信頼を再構築する
- 3. テレアポが再接点創出に強い理由
- 3.1. なぜメールやDMでは反応しにくいのか?
- 3.2. テレアポの特性:記憶の喚起と目的の明確化
- 3.3. 効果的なトーク設計のポイント
- 3.4. NGトークの例と対策
- 3.5. テレアポが持つ「人の声」の価値
- 4. 成果につながる“掘り起こし設計”3つのステップ
- 4.1. STEP1:ターゲットのセグメントを再設定
- 4.2. STEP2:スクリプトと資料を“復帰前提”にチューニング
- 4.3. STEP3:アポ獲得→商談につながる情報収集の仕組み化
- 5. 休眠顧客アプローチを“仕組み化”するには?
- 5.1. なぜ社内リソースだけでは限界があるのか?
- 5.2. 接点創出を外部化するという選択肢
- 5.3. アポ代行を“チームの一員”として活用する
- 5.4. 休眠顧客アプローチを仕組み化するための一歩
- 6. まとめ

目次
なぜ休眠顧客は“難しく”見えるのか?
「以前は良好な関係だったのに、最近はまったく話が進まない」。これは多くの営業担当者が一度は感じたことのある課題ではないでしょうか。
BtoBにおける休眠顧客とは、「まだ受注に至っていない潜在顧客」だけでなく、「一度取引があったが、しばらく関係が途絶えている顧客」も含まれます。たとえ過去にやり取りがあったとしても、再び接点を作るには新たな課題が浮上するのです。
なぜ、休眠顧客が“難しく”見えるのか?
ひとつには、放置状態=無関心ではないという点が挙げられます。休眠している間、顧客側も社内事情や予算状況が変化しているため、以前のアプローチ方法が通用しなくなっているケースが多いのです。加えて、営業担当者が「休眠=温度が低い」と決めつけてしまうことが、再アプローチの妨げになっています。
実際には、過去にやり取りした経験がある分、全くの新規顧客よりも信頼構築がしやすいはずですが、そのポテンシャルを見落としてしまうと、結果として「難しい顧客」と認識されがちです。
再接点を作るきっかけが重要
もう一つの要因は、「再接点を作るきっかけが不足している」ことです。休眠顧客は、単なる放置状態から商談化するわけではありません。再び接点を持つためには、最初の接触タイミングや話す内容、提供する価値の再定義が必要です。ここが明確でないと、どれだけ連絡しても返事が来ず、次第に営業側も手を止めてしまうことになります。
営業現場での勘違いに注意
営業担当者の間では、「休眠=冷たいリード」「休眠顧客は興味がない」という思い込みが少なくありません。ところが、実際には、休眠しているのは興味が薄れたからではなく、営業が顧客の現状や課題に適した接点を作れていない場合がほとんどです。この誤解を解消し、適切な接点設計に取り組むことが、休眠顧客を商談化へと導く第一歩です。
キーワードを活かした営業戦略へ
「休眠顧客 営業戦略」「BtoB 営業 顧客管理」などの視点を踏まえ、休眠顧客が“難しい”と感じられる背景を理解し、そこから再接点を設計することで、営業効率を飛躍的に向上させることができます。
次章では、実際に成果を出している企業が実践する、休眠顧客掘り起こしの具体的なアプローチについて解説していきます。
掘り起こし成功企業の共通点とは?
休眠顧客を商談化に結びつけている企業には、いくつかの共通する考え方と行動があります。これらは、単に「接触回数を増やす」だけでなく、顧客の状況を再評価し、効果的なアプローチを設計している点に特徴があります。
顧客を再評価する:過去ではなく現在に注目する
成果を上げている企業はまず、休眠顧客の現状を再評価しています。その際に重要なのは、「現在の状況」と「当時の状況」の違いを明確にすることです。
・過去の離脱理由を掘り下げる
なぜ取引が終了したのかを確認します。「他社と比較して選ばれなかったのか」「タイミングが合わなかったのか」「社内の事情で導入が見送られたのか」など、理由を特定することで、次回のアプローチのヒントが得られます。
・顧客ステータスを現在の目線で再分類する
単に「休眠」扱いではなく、
1. 再接点が容易で早期商談化が期待できる顧客
2. 条件調整が必要な顧客
3. 長期的なフォローが必要な顧客
といった形で分けることが、効率的なアプローチ設計につながります。
掘り起こしの切り口を分ける:休眠理由に合わせたアプローチ
成功している企業は、「休眠顧客全体」を一括して扱うのではなく、休眠理由に応じたアプローチをしています。
・タイミングが合わなかった場合
例えば、教育機関向け商材を扱う場合、年度末や新学期前など特定のタイミングで再提案を行う企業が成果を上げています。適切な時期に、予算化や計画立案のタイミングを見越してアプローチすることが効果的です。
・他社を選んだ場合
以前は価格や機能で競合他社に負けた顧客も、新たな機能改善や価格体系の見直し、実績増加を示すことで再び興味を持ってもらえる可能性があります。顧客視点に立った比較表や新事例を用いるのが有効です。
・社内事情で保留された場合
担当者が変わったり、社内方針が変わったケースでは、新しい担当者や決裁者とつながることがポイントです。この場合、関係構築から始め、過去のやり取りを丁寧に説明することで信頼を取り戻します。
休眠理由別のアプローチ方法
①タイミングが合わなかった場合
過去に「時期尚早」と判断された顧客には、事前に年次スケジュールを確認し、予算編成時や年度切り替え時に合わせた提案を行うのが効果的です。また、新製品やキャンペーンのタイミングに合わせて再度連絡することで、より興味を引きやすくなります。
②競合に流れた場合
競合との差別化が曖昧だったために取引を失った顧客には、自社の強みを明確に伝える必要があります。他社の導入事例や、自社が解決した具体的な課題を示すことで、「今なら価値がある」と思わせることができます。
③社内事情で保留された場合
担当者の異動や社内方針の変更による休眠顧客には、まず最新の担当者情報を確認し、現状の課題や方針に合わせた新しい提案を作ることが鍵となります。現場の事情が変わっている可能性があるため、ヒアリングを行いながら再提案の基盤を整えます。
CRM・SFAツールを活用した掘り起こし戦略
掘り起こし成功企業のもうひとつの共通点は、CRM(顧客関係管理)やSFA(営業支援システム)を活用していることです。
・過去のやり取りや失注理由を正確に記録
・次回アプローチのタイミングや条件を可視化
・営業チーム全体で進捗状況を共有し、重複や漏れを防止
・リマインダー機能を利用して、適切なタイミングでフォローアップ
これにより、過去のやり取りを活かしつつ、的確なタイミングで再接触が可能となります。また、全体のプロセスが整理されているため、営業チームが一丸となって掘り起こし活動を進めやすくなります。
掘り起こし戦略の本質:信頼を再構築する
掘り起こし成功企業が実践しているのは、単に「連絡頻度を上げる」ことではなく、顧客との信頼関係を再構築することです。そのためには、過去の失注理由を明確にし、現在の状況に合わせた提案を行い、顧客の課題に即した接点を設計することが必要です。
次章では、実際の具体例をもとに、どのようにして掘り起こし戦略を実行していくかを解説します。
テレアポが再接点創出に強い理由
「休眠顧客」を再接点に引き戻す手法として、メールやDMではなくテレアポが最適解となる場合が多い理由は、その“記憶喚起”と“目的の明確化”にあります。
なぜメールやDMでは反応しにくいのか?
メールやDMは一度に多くの顧客にアプローチできるため効率的に思えますが、休眠顧客には刺さりにくい一面があります。その理由の一つが、「関係はあっても“今すぐ”必要ではない」という状況です。
たとえば、以前に取引があった企業でも、現在は他社と契約中であったり、担当者が変わっていたりすることがあります。そのため、「資料を送るだけ」や「お知らせメール」では、優先度の低い情報としてスルーされてしまう可能性が高いのです。
テレアポの特性:記憶の喚起と目的の明確化
一方、テレアポは記憶を呼び起こす力と明確な目的を示す力を同時に発揮します。実際の声を通じて「以前の取引先」としての記憶を喚起し、さらに現在進行中の課題やタイミングにフォーカスした具体的な提案を伝えることで、再接点の糸口を作ることが可能です。
例えば、休眠顧客へのテレアポで「以前導入いただいたツールが、今年さらに改良されました」といった具体的な改善点や導入事例を提示すると、顧客側は「また話を聞いてみようか」と前向きな気持ちになることがあります。このように、声の温度感と具体性はメールやDMにはない強みです。
効果的なトーク設計のポイント
効果的なテレアポのトーク設計にはいくつかの要素があります。以下は成功している企業が取り入れている要素の例です:
・過去の文脈を活用する
「以前の資料が新しくなったのでお送りします」や「昨年度も同じタイミングでご検討いただいていた件で…」など、過去のやりとりを起点にすることで、話がスムーズに進む傾向があります。
・タイミングを意識する
「今年は導入事例が増えているので一度ご確認いただければ」といった、タイムリーな情報を提供することで関心を引きやすくなります。
・担当者変更の情報を盛り込む
「ご担当が変わられたとのことで、改めてご挨拶も兼ねてお話しさせていただきます」といった内容は、特に人事異動が多い時期に効果的です。
NGトークの例と対策
効果的なテレアポトークを作るためには、避けるべきアプローチも把握しておく必要があります。
NGトーク例:
・「以前お世話になったのでまたお話しませんか?」とだけ言う
・明確な提案内容や話す目的がないまま、とにかく電話する
対策:
・必ず「なぜ今お話ししたいのか」を明確にする
・過去の取引内容や顧客の背景を調べ、話すきっかけを作る
・アポ後に役立つ情報を提供する姿勢を示す
テレアポが持つ「人の声」の価値
テレアポは単なる接点作りの手段ではなく、顧客との信頼を再構築するツールです。営業担当者の声には、相手の温度感や興味を見極める力があり、これはメールやDMでは代替しにくい特性です。
特に休眠顧客に対しては、「今すぐ検討する必要はない」と思っている相手に再び振り向いてもらうには、具体的な価値を伝えられる“生の声”が効果を発揮します。そうすることで、もう一度商談のテーブルに乗せる可能性が高まるのです。
このように、テレアポは記憶の喚起や目的の明確化、信頼の再構築といった要素を兼ね備えた強力な手段です。次章では、さらに具体的なスクリプトや進め方の事例について掘り下げていきます。
成果につながる“掘り起こし設計”3つのステップ
休眠顧客を商談に引き戻すためには、ただ接触回数を増やすだけでは不十分です。成果につながる掘り起こしには、計画的な設計が不可欠です。以下では、具体的な3つのステップを紹介します。
STEP1:ターゲットのセグメントを再設定
まず初めに、ターゲットを正確に絞り込むことから始めます。単に「過去に取引があった顧客」を一括りにせず、以下のような分類で再設定します:
・過去の対応履歴
最後の接触時期、担当者名、やり取り内容などを確認し、具体的な履歴に基づいて優先順位をつけます。
・前回の商談フェーズ
過去にどの段階で止まったのか(価格面で折り合わなかった、導入時期が合わなかったなど)を把握することで、再提案時のアプローチポイントが明確になります。
・導入業界や利用用途
特定の業界や用途に強い自社商材であれば、それに合ったセグメントに絞り込むことで、再接触後のヒット率を向上させます。
STEP2:スクリプトと資料を“復帰前提”にチューニング
次に、再接触用のスクリプトや資料を見直します。特に重要なのは、休眠顧客を復帰させる前提でのトーク設計です。
・説明トークを最小化
以前のやり取りで基本的な情報は伝わっているため、詳細な説明を繰り返す必要はありません。代わりに、「今回再接触した理由」を明確に伝えることで、話の腰を折らずに次の段階へ進みやすくします。
・前向きな理由を軸に
「この数年間で市場ニーズが変わり、新たな活用事例が増えてきました」「最新バージョンでは導入負担が軽減されました」など、顧客にメリットを感じてもらえる前向きな理由を話の中心に据えます。
・資料の簡潔化とポイント提示
過去に使用した提案資料も、復帰を促す視点でアップデートします。「これまでのお付き合いを踏まえた新たな提案」として、ポイントを絞った資料にすることで、商談の入り口がスムーズになります。
STEP3:アポ獲得→商談につながる情報収集の仕組み化
最後に、アポ取得から商談までのプロセスで情報収集を仕組み化します。この段階では、「次のステップへつなげるためのデータ」を集め、チーム全体で活用できる環境を整えます。
・ヒアリング項目のテンプレ化
「現状の課題」「直近での変化」「導入の決裁プロセス」など、商談に必要な情報を網羅したテンプレートを用意します。これにより、再接触時に得た情報を確実に商談に結びつけられます。
・商談率を高めるレポート共有
アポ代行からのフィードバックを受け、営業チーム全員が共有できるレポート形式で情報をまとめます。これにより、次の商談段階で無駄な情報の重複やミスを防ぎ、確実に進める体制が整います。
休眠顧客を活性化させるには、闇雲に連絡するのではなく、計画的な「掘り起こし設計」が必要です。ターゲットのセグメントを細分化し、トークと資料を復帰前提に最適化し、商談につながる情報収集の仕組みを整える。この3つのステップを実行することで、休眠顧客を再び商談に導くチャンスが広がります。
休眠顧客アプローチを“仕組み化”するには?
休眠顧客を継続的に掘り起こし、成果を上げるためには、属人的な対応から脱却し、再現性の高い営業体制を構築する必要があります。ここでは、企業が直面する課題と、それを克服するための実践的な方法について解説します。
なぜ社内リソースだけでは限界があるのか?
多くの企業が、休眠顧客へのアプローチを試みますが、日々の業務の中でこれを継続的に行うのは至難の業です。その主な理由は以下の通りです:
・リソース不足
営業担当者は、既存顧客のフォロー、新規開拓、提案準備などに忙殺され、休眠顧客の掘り起こしまで手が回らない。
・優先順位の問題
即時性のある案件や「見込み度の高い」顧客対応が優先され、休眠顧客は後回しになりがち。
・ナレッジの散逸
過去のやりとりや接点の記録が断片的で、どのような切り口でアプローチすれば良いのかが見えづらい。
結果として、「掘り起こし」は一時的なキャンペーンにとどまり、本来の商機を逃すケースが少なくありません。
接点創出を外部化するという選択肢
こうした課題に直面した際、考慮すべきは「接点創出」の部分を外部化するアプローチです。これは単なる業務負荷の軽減にとどまらず、より精度の高い掘り起こしを可能にします。
・外部化のメリット
専門知識を持つチームが、顧客管理情報や市場データを活用して、最適なタイミングで再接触を行います。
・効率的な情報収集
ヒアリング結果を整理し、商談に直結する形で営業チームに共有。これにより、再接触後の商談成功率が向上します。
・営業活動のフォーカス
営業担当者は提案やクロージングに集中できるようになり、より戦略的な対応が可能になります。
アポ代行を“チームの一員”として活用する
アポ代行の効果を最大化するためには、単なる外注ではなく、営業チームの一員として捉える発想が重要です。
具体的には次のような連携が求められます。
・役割の明確化
営業担当者は提案やクロージングに専念し、アポ代行チームが初回接点の設計・実行を担当する明確な分業体制を確立。
・ナレッジの共有
アポ代行からのヒアリング内容や接触後の顧客反応を、定期的なレポートとして社内で共有し、次の営業アクションに活用。
・KPIの設定
「単なるアポ数」ではなく、「商談化率」や「提案後の受注率」といった、より成果に直結する指標でパフォーマンスを評価する。
休眠顧客アプローチを仕組み化するための一歩
最初の一歩として重要なのは、既存の営業フローの見直しです。
たとえば、以下のようなチェックリストをもとに現在の取り組みを評価してみてください。
【チェックリスト例】
✅ 休眠顧客のリストは最新の情報で更新されているか?
✅ 再接触するための適切なタイミングが設定されているか?
✅ 過去のやりとりを反映したスクリプトが用意されているか?
✅ 再接触後のヒアリング内容が商談に活用されているか?
✅ 外部パートナーと効果的な情報共有ができているか?
休眠顧客アプローチを仕組み化するには、単に外部リソースを使うだけでなく、「チームとしての連携」と「ナレッジの活用」が不可欠です。このような取り組みを実践することで、再現性の高い営業体制を構築し、休眠顧客から新たな商機を引き出すことが可能になります。
まとめ
休眠顧客は“受注可能性が低い相手”ではなく、“きっかけが途絶えていただけの有望層”です。成果を出す企業は、営業リソースを疲弊させることなく、「再接点の質」から営業設計を見直しています。
タノメイトは、BtoB・教育機関営業に強みを持つ“初回接点のプロフェッショナル”として、過去の文脈を活かしたヒアリングと商談創出を支援。
CRMデータを起点に、役職・時期・トーク設計を最適化し、“再び話せる関係”を確実に作り出します。
「放置したままの顧客と、もう一度商談したい」
そう思った瞬間が、営業再設計のベストタイミングです。
👉 https://tanomate.net/ – アポ代行の新しい形を、ぜひご確認ください。

タノメイト編集部です。テレアポのプロの視点から、テレアポに関するさまざまな情報をわかりやすく発信します。
【タノメイトとは?】
タノメイトは「質の高いリード獲得」にこだわる、成果報酬型テレアポ代行サービスです。リード獲得にお悩みの企業様はぜひお問い合わせください。
商談につながるアポを獲得
完全成果報酬型テレアポ代行
『タノメイト』
● 初期費用・固定費0円
リードを獲得した分だけお支払い。完全成果報酬型でリスクゼロだから今すぐ始められます。
● 質の高いリード獲得
成功事例に基づくスクリプトと精度の高いリストを活用。質の高いリードを獲得します。
● 安心のキャンセル保証
条件をクリアしたリードのみご案内。条件を満たさないリードはキャンセル可能です。

\ リスクゼロで始めるテレアポ代行 /