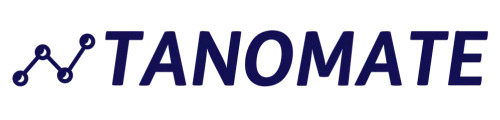自治体は電話に出ない!?プロの力で商談機会を獲得する方法
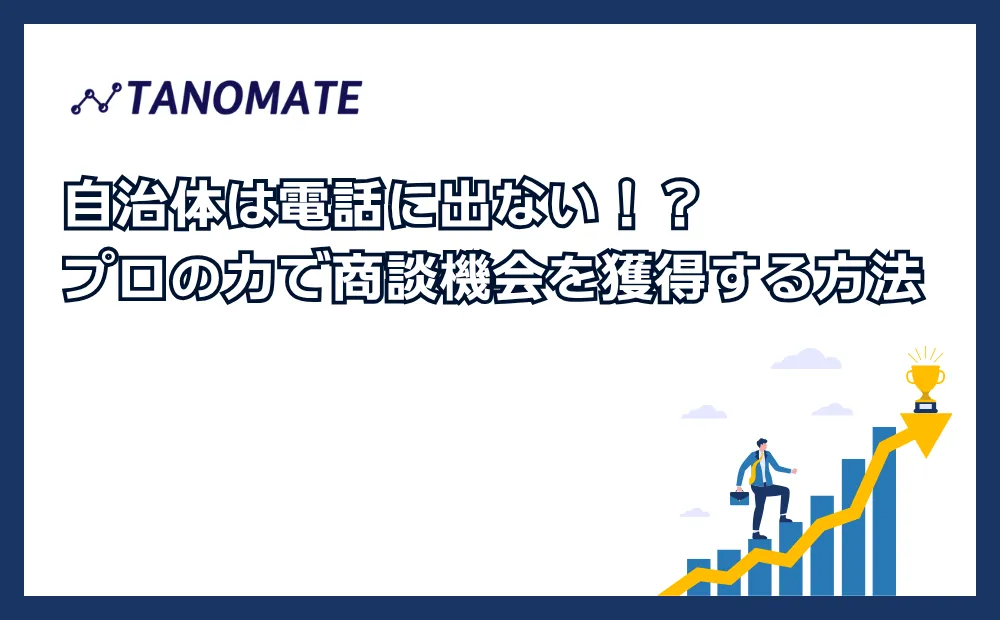
自治体との取引は安定性や信頼性が高く、企業にとって魅力的なビジネスチャンスです。しかし、実際の営業現場では「電話がつながらない」「担当者にたどり着けない」といった壁に多くの企業が直面しています。本コラムでは、“つながらない自治体営業”をどう突破するかをテーマに、プロのアポ代行によるアプローチ手法や成功事例、実践ポイントを詳しく解説します。自治体案件の商談機会を獲得したい企業様必見の内容です。
- 1. はじめに
- 2. 自治体営業における「電話がつながらない」実情
- 2.1. 自治体特有の業務体制と制約
- 2.2. 自社営業での限界
- 3. なぜアポ代行が自治体営業に効果的なのか
- 3.1. 専門性のあるオペレーターが対応
- 3.2. タイミングと戦略をコントロール
- 3.3. リスト設計・トーク設計の工夫
- 4. アポ代行ができること・期待できる成果
- 4.1. アポ獲得だけじゃない!自治体営業の全体支援
- 4.2. 現場で実際に起こっている成果例
- 4.3. 担当者との接点数を増やすことの重要性
- 5. アポ代行を成功させるためのポイント
- 5.1. 代行会社の選定基準
- 5.2. 自社の営業体制との連携がカギ
- 6. 成功事例:アポ代行で突破した自治体案件
- 6.1. IT企業が自治体DX推進プロジェクトで15件の商談を創出
- 6.2. 人材会社が教育委員会との接点構築に成功し、職員研修を受注
- 6.3. 両社に共通していた「成功の方程式」
- 7. まとめ

目次
はじめに
営業活動において、自治体案件は多くの企業にとって非常に魅力的なターゲットです。その理由は明確で、一度取引が成立すれば長期的な契約につながる可能性が高く、契約相手としての信用力も抜群。さらに、自治体との実績は他の営業先にも好印象を与えやすく、企業ブランディングにも寄与します。安定性・信頼性・将来性の三拍子がそろった市場であることから、特にIT・人材・コンサルティング業界では自治体案件の獲得が大きな目標となっているケースも少なくありません。
しかし、自治体営業には独特の難しさが存在します。その最たるものが「電話がつながらない」という現実です。多くの営業担当者が、何度も架電しても担当者不在、代表窓口では詳細がわからず、ようやくつながったとしてもすぐに商談には進めないという状況に直面しています。自治体職員は会議や外出、窓口対応などで日中は多忙を極めており、一般企業のようにスムーズな対応を期待するのは困難です。この「接点すら持てない」状態は、営業の出鼻をくじき、貴重な商談機会を逸する大きな原因となっています。
そこで注目されているのが、自治体営業に強みを持つ「アポ代行サービス」の活用です。プロのオペレーターが、自治体の特性に合わせたタイミング・言葉遣い・アプローチ方法でアポイントを獲得し、企業の営業担当が商談に集中できる状態を整えてくれます。電話がつながらないという問題を、専門の人員とノウハウで“突破”する仕組みが、今あらためて注目されています。
本コラムでは、自治体案件の営業でつまずきやすい「つながらない壁」の正体と、それを乗り越えるためのアポ代行活用術について、具体的な方法や事例を交えて解説していきます。自治体営業に取り組んでいる、あるいはこれから強化したいと考えている企業様は、ぜひ参考にしてください。
自治体営業における「電話がつながらない」実情
自治体との取引は、信頼性や安定性の面で企業にとって大きな魅力があります。しかし、実際の営業現場では、「電話がそもそもつながらない」という基本的な壁に多くの営業担当者が直面しています。民間企業であれば比較的スムーズに担当者に繋がるケースも多いですが、自治体はその構造や業務体制がまったく異なり、通常の営業フローが通用しないのが現実です。本章では、その“つながらない”理由と、自社営業だけでは突破が難しい背景を解説します。
自治体特有の業務体制と制約
民間企業であれば、営業電話が代表番号から営業部門にスムーズに転送されることは珍しくありません。営業担当が常駐していたり、社内チャットや転送で迅速な折り返しがなされる体制が整っているからです。
しかし、自治体ではこの常識がまったく通用しません。自治体特有の組織構造や勤務体制は、民間とは大きく異なるため、電話営業を試みるだけでも一筋縄ではいかないのが現実です。
✅ 会議・外出・窓口対応で常に多忙な担当者
自治体職員の業務は幅広く、かつ頻繁に変動します。たとえば、ある部署の担当者は1日のうち数時間にわたって庁内会議やプロジェクトの打ち合わせ、関係機関との調整に追われ、デスクにいる時間が極端に短いことも珍しくありません。さらに、市民窓口業務や現場対応、現地調査への外出など、日常的に席を外す業務が多数存在します。
このように、電話に出られる時間が限られているだけでなく、電話の優先順位そのものが低いのです。つまり、架電しても「出られない」のではなく、“対応する余裕がない”というのが実情です。
✅ 「代表電話=情報の壁」問題
多くの自治体は、まず代表番号や総合窓口を通して電話を受け付ける体制を採っています。しかしこの窓口は、市民対応・行政手続きの問い合わせなど、日常的に膨大な電話が寄せられているため、営業目的の電話は取り次ぎが拒否されるケースも多く見受けられます。
さらに、以下のような対応が実際に行われています。
「その部署には直接おつなぎできません」
「担当者名がわからないと取次はできません」
「メールで問い合わせをお願いします(電話NG)」
このような情報の遮断や物理的な取次制限によって、営業側が本来接触したいキーマンにたどり着くまでに何重ものハードルが設けられているのです。
✅ 公平性の原則と“特別扱いNG”の文化
自治体は公的機関であるため、一部の企業だけを優遇するような対応はしづらいという「公平性の原則」が常に働いています。そのため、「●●社さんからお電話です」といった紹介でも、他の問い合わせと同列に扱われ、迅速に取り次がれることは稀です。
また、官公庁特有の文化として「前例を踏まえる」「手順を守る」ことが重視されており、イレギュラーな対応や臨機応変な判断がしにくいという点もあります。たとえ自治体側に興味を持ってもらえていたとしても、電話で即対応、即アポという展開にはほとんどなりません。
✅ 実態を踏まえた営業スタンスの再構築が必要
こうした自治体特有の制約に対して、「民間と同じようにアプローチすればうまくいく」と考えるのは危険です。そもそも“電話が通じない・繋がらない・取り次がれない”という構造が存在する中で、自社の営業体制だけで突破しようとするのは限界があるのです。
特に、自治体案件に不慣れな企業では、「なぜこんなに反応が悪いのか?」「本当に興味がないのか?」と誤解し、貴重な見込み案件を見過ごしてしまうリスクもあります。
このような“見えない壁”をどう突破するかが、自治体営業成功のカギとなります。
自社営業での限界
自治体への営業は、民間企業とはまったく異なるアプローチが求められます。その中でも特に大きな壁となるのが、「接点を持つこと自体が極めて難しい」という現実です。企業側がどれだけ良質なサービスや提案を持っていたとしても、担当者にたどり着けなければ、その魅力は伝わりません。実際、多くの営業担当者が以下のような悩みを口にしています。
「1日3回架電しても全て不在。翌日も同じ。」
「代表窓口にかけても、“担当課におつなぎできません”の一点張り。」
「やっとつながったと思ったら“その件は別部署です”と回され、また最初からやり直し。」
このような状況が続くと、営業担当者のモチベーションや生産性は著しく低下します。そしてさらに厄介なのが、自治体側からの“折り返し連絡がほとんどない”という点です。営業電話が多いことを理由に、折り返し対応を後回しにされることも多く、担当者と接点を持つために1週間、2週間とただ待つだけになってしまうことも珍しくありません。
さらに、自治体には独特の“異動文化”もあります。毎年4月、10月などのタイミングで大規模な人事異動があるため、せっかく話が進んでいた担当者が突然異動し、話がゼロに戻るという事態も頻発します。民間企業のように営業日報が引き継がれているわけでもないため、関係性は「個人ベース」で成り立っており、一人の異動が営業機会を一気に断ち切ってしまうリスクがあるのです。
こうした背景から、自治体営業では「架電回数を増やせば成果が出る」といった単純な発想は通用しません。電話をかけても出ない、出ても取り次いでもらえない、折り返しもない、担当者は不在や異動続き——こうした連鎖によって、そもそも“商談の入り口”にすら立てない状態が生まれます。
このように、自社の営業担当が片手間で自治体営業を行うのは、時間と労力がかかるうえ、成果が出るまでに膨大なストレスがかかるというのが実情です。中には、「案件は欲しいが、自治体営業は非効率だからやめた」という声も少なくありません。
しかし、自治体案件の魅力(安定性・長期性・信頼性)は非常に高く、あきらめるには惜しいマーケットです。だからこそ、「電話がつながらない」という構造的な問題を乗り越えるには、次章で解説するようなプロフェッショナルによるアポ代行の導入が、現実的で有効な選択肢となってきます。
なぜアポ代行が自治体営業に効果的なのか
「自治体は電話に出ない」という問題は、禁断架電回数を増やそうと解決するものではありません。自治体文化ならではの言葉遣いや決裁フローに対して冷静にアプローチし、相手の立場に配慮したコミュニケーションをとることが求められます。そこで効果を発揮するが、自治体営業に精通した「アポ代行業社」の活用です。
アポ代行は単なる「電話代行」ではなく、戦略的に商談の機会を生み出す営業支援パートナーです。本章では、自治体で営業でアポ代行が効果的な理由を3つのポイントに分けてご紹介します。
専門性のあるオペレーターが対応
自治体営業は、限定電話をかけるだけでは成果につながりません。自治体独自の文化や言葉遣いに配慮し、相手に「信頼される印象」を考慮した対応力が求められます。
アポ代行では、自治体案件に精通したオペレーターがし、以下のような専門的な対応を行います。
・「御庁」や「ご担当課」など、公的機関特有の丁寧な敬語表現の徹底
・予算時期・会議スケジュールなど、自治体への重点を置いた対応
・「ご説明の機会をいただけませんか」といった柔らかい表現での提案
このような対応を行うことで、自治体側にも「この会社はちゃんとしている」という好印象を与え、第一印象の段階で関係構築のきっかけを作ることが可能になります。
タイミングと戦略をコントロール
電話がつながらない最大の原因のひとつは、自治体側のスケジュールと合っていない時間帯に架電してしまっていることです。 アポ代行では、過去の架電データや自治体の勤務傾向をもとに、つながりやすい時間帯を戦略的に目指してアプローチします。
【自治体職員の「つながりやすい時間帯」傾向
| 時間帯 | 繋がる確率 | 備考 |
|---|---|---|
| 9:00-10:00 | 低 | 朝礼や市民対応が立て込む |
| 10:00-11:30 | 高 | 比較的電話が繋がりやすい |
| 12:00-13:00 | 中 | 昼休憩と重なり対応者が制限される |
| 14:00-16:00 | 高 | 午後の業務が落ち着くタイミング |
| 16:30以降 | 低 | 業務終了間際で取次が避けられる |
このような「自治体営業のゴールデンタイム」を狙って架電できるのは、時間を限定せず活動できるアポ代行の強みです。
リスト設計・トーク設計の工夫
アポ代行が成果を出す最大の理由の一つが、事前準備の質の高さです。 自治体案件は、アプローチ展開・外交・地域によってニーズも関心も大きく異なります。
《アポ代理による戦略的な準備の例》
・ターゲットリスト作成
「地域福祉」「教育」「防災」「観光振興」など、商材に合った展開に絞り込み
・トークスクリプト設計
地域課題・国家潜在(例:デジタル田園都市構想)・補助金制度に絡めた訴えポイントを明確化
・提案タイミングの調整
予算編成前や補助金募集の時期など、関心が高まるタイミングを狙って架電
このように、「誰に・いつ・どう伝えるか」まで徹底的に最適化する仕組みが整っているため、自社で行う場合と比べて圧倒的に接点獲得率が高くなるのです。
自治体営業における「電話がつながらない」課題を突破するには、専門性・タイミング・戦略設計の3点が欠かせません。次章では、アポ代行が実際にどのような業務を担い、どのように成果を生み出すのか、具体的な業務領域と期待できる効果について詳しく解説していきます。
アポ代行ができること・期待できる成果
「アポ代行=アポイントだけのサービス」と思われることが多いですが、実際にはそれ以上に自治体営業全体を支援し、商談チャンスを広げる土台を築くまで対応している業者もあります。
本章では、アポ代行が担っている業務の範囲と、クライアント企業が得ている具体的な成果について解説します。
アポ獲得だけじゃない!自治体営業の全体支援
アポ代行は、「アポイントだけ」の存在ではありません。 代行業社の中には、自治体営業の開始から商談の接続までを連続のプロセスとして一括対応している業者もあります。以下のようなステップを踏むことで、「接点ゼロ」の状態から「商談設定」までをスムーズに導くことが可能です。
▶ アポ代行が行う営業プロセスの一例
| ステップ | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 資料送付 | 自治体のニーズに合致した簡易資料を送付(業者により) | 興味喚起・話を聞くきっかけ作り |
| 折り返しリクエスト | 電話で担当者が出ない場合、時間を変えてアプローチ | 接触の動線を作る |
| 会社情報の取得 | 架電や資料送付先を特定・キーマンの特定 | 次回以降のターゲッティング精度向上 |
| アポ確定 | スケジュール調整と話題整理 | 商談の設定完了 |
このように、代行業社によっては「まずは担当者の名前が分からない」状態からでも、段階的に関係を構築し、商談に結びつける仕組みを構築できます。
現場で実際に起こっている成果例
実際にテレアポ代行を導入したA社では、以下のような具体的な成果が出ています。
| 項目 | 自社対応時間 | テレアポ代行導入後 | コメント |
|---|---|---|---|
| 月間アポ数 | 平均2〜3件 | 平均8〜12件 | 効率が大幅に改善 |
| 担当者名取得率 | 約30% | 約65% | 継続的なアプローチで情報取得 |
| 初回商談までの平均日数 | 約20日 | 約1週間 | 適切な架電時間帯・頻度を調整 |
特に自治体営業では、「誰に話すか」「いつ話すか」が受注確率に直結するため、「初動の接点創造」ができるかどうかで結果は大きく変わります。
担当者との接点数を増やすことの重要性
自治体案件の多くは、タイミングが命です。予算確保の時期や事業立ち上げのタイミングに合致しなければ、どれだけ良い提案でも「今は難しい」で終わってしまいます。そのため、定期的な接点づくり=受注の可能性をつなぐ活動になります。
テレアポ代行では、以下のような成果につながるアプローチを実施しています。
・担当者が出る時間帯を考えて、淀みなく再架電
・「少し興味あり」の反応があった自治体に数週間後に再び接触
・複数の配置に横展開し、接点を増やす
自治体は一度関係性が築けると、リピートにも繋がりやすい市場です。その最初のきっかけとなる「1回のアポイント」を獲得することが、テレアポ代行の最大の役割です。
アポ代行を成功させるためのポイント
自治体営業においてテレアポ代行を導入する企業は年々増加していますが、その成果は「誰に依頼し、どう活用するか」によって大きく異なります。単に「電話をかけてもらう」だけで終わる代行と、自社営業の一部として機能させる代行とでは、最終的な成果に大きな差が出るのです。
ここでは、自治体案件の獲得を目指すうえでアポ代行を効果的に活用するためのポイントを、2つの視点から解説します。
代行会社の選定基準
まず最も重要なのが、どのテレアポ代行会社と組むかです。自治体向け営業には、民間営業とは異なる“前提知識”と“配慮”が求められます。たとえば、話し方一つで担当者の印象が大きく変わる自治体相手には、言葉遣いや対応姿勢、情報の伝え方が洗練されたオペレーターが必須です。
以下のような視点で選定すると、失敗リスクを最小限に抑えられます。
| 選定基準 | チェックポイント | 見極めの理由 |
|---|---|---|
| 自治体営業への理解 | 自治体案件の実績はあるか? 専門部署があるか? | 決済構造・予算時期・対応文化を理解しているかが鍵 |
| アポの「質」へのこだわり | 単なる件数重視ではなく、商談化率を意識しているか? | “話せる”だけでなく“次に繋がる”アポを提供できるか |
| フェードバック体制 | 架電記録・反応・温度感のレポートがあるか? | 現場の声を自社営業に活かせるがどうかが変わってくる |
多くの代行会社が「月間◯件のアポを保証」といった件数ベースの成果を強調しますが、自治体営業では“数よりも質”が重要です。可能性が見込めるアポかどうか、ターゲットが適切か、タイミングは合っているか――この3点を外すと、アポの“消化試合”が増えるだけで、受注にはつながりません。
自社の営業体制との連携がカギ
テレアポ代行から商談アポが入ったとしても、その後の自社対応が雑だったり遅れたりすれば、相手の温度はすぐに冷めてしまいます。代行を「頼んで終わり」にせず、“社内でどう活かすか”の準備と体制づくりが、成果の最大化に直結します。
✅ アポ後の対応フローをあらかじめ設計する
商談アポを得たら、その後に必要なのはスムーズで信頼感のある対応です。誰が対応するのか、どの資料を使うのか、どんな話をするのかを事前に決めておきましょう。
| タイミング | 対応内容 | 担当者 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アポ取得後 | 架電内容・反応の社内共有 | 営業事務or担当営業 | レポート内容を必ず確認 |
| 商談前日 | ヒアリング内容をもとに準備 | 担当営業 | 想定問答・導入事例を事前に準備 |
| 商談当日 | 提供・ヒアリング・クロージング | 担当営業 | 次のアクション提示内容を決めておく |
このように“アポを取る”と“商談を進める”をシームレスに連携させることが、成果の再現性を生む第一歩となります。
✅ フィードバックを営業戦略に活かす
テレアポ代行の現場では、アポが取れなかったとしても、部署名・担当者の在席傾向・関心テーマ・今後の検討時期など、次回アプローチに活かせる情報が蓄積されます。これを放置してしまうのは大きな損失です。逆に、こうした情報を営業戦略に活かせば、
・「教育関連部署は7月以降に予算決定が進む」
・「防災部門は防災訓練後が提案タイミング」
・「DX系サービスは情報政策課より財政課が窓口だった」
といった、“案件化しやすい条件”が見えてきます。このように、フィードバックを分析・反映・改善に活かす仕組みがあるかどうかで、アポ代行の効果は大きく変わってくるのです。
次章では、実際にこれらのポイントを実践し、アポ代行の導入を通じて商談数・受注率ともに向上させた企業の成功事例をご紹介します。自治体営業の成果につなげるヒントを、ぜひご確認ください。
成功事例:アポ代行で突破した自治体案件
「自治体は電話に出ない」——これは多くの企業が自治体営業で直面する“最初の壁”です。しかし、この壁を乗り越え、商談機会を着実に生み出している企業も存在します。彼らの共通点はただ一つ。アポ代行を単なる外注先ではなく、“戦略的パートナー”として協業していたことです。
ここでは、当社が実際に支援した企業2社の成功事例をご紹介します。いずれも、自治体営業の特性を理解し、自社の動きとテレアポ代行の動きを連携させることで、高い成果を上げた事例です。
IT企業が自治体DX推進プロジェクトで15件の商談を創出
このIT企業は、行政の業務効率化を支援するSaaSを提供しており、自治体のDX化支援に注力していました。しかし、担当者に接触できず、商談の機会すら得られない状況が続いていました。
そこで当社の自治体特化型テレアポ代行を導入。導入初期から営業チームと密に連携し、
・DX関連部署のターゲット選定
・補助金タイミングに合わせた架電戦略
・担当者の反応を見ながらのトーク内容改善
といった調整を週単位で実施。
その結果、3か月で15件の商談機会を創出。うち4件が導入検討フェーズに進展しました。
| 成果指標 | 導入前 | テレアポ代行導入後 |
|---|---|---|
| 月間アポ数 | 平均3件 | 平均8件以上 |
| 担当者名取得率 | 約25% | 約80% |
| 商談化率 | 10%以下 | 約30% |
人材会社が教育委員会との接点構築に成功し、職員研修を受注
自治体向けに職員向け研修を提供するこの人材会社は、「誰に話せばいいのか分からない」「教育委員会への連絡がブロックされる」といった課題に苦戦していました。当社が対応したのは、代表窓口の突破と担当者名の取得、関心テーマの探り出しです。加えて、企業側も次のような取り組みを行いました。
・営業資料を“教育委員会向け”に特化して再設計
・担当者の反応に応じてスクリプトをカスタマイズ
・アポ取得後、営業が即日フォローで訪問またはWeb商談へ接続
結果、1か月で10以上の教育委員会との接点が生まれ、2件の研修導入が決定。さらに2件が次年度検討枠に入りました。
💡ポイント
現場の声を活かし、営業資料と話法を柔軟にチューニング。代行が得た“気づき”を営業にフィードバックし、対応の精度を高めた点が勝因となった。
両社に共通していた「成功の方程式」
| 成功要因 | 内容 |
|---|---|
| 戦略的なターゲット選定 | 自治体の部署・関心分野を明確にし、代行とすり合わせる |
| 代行と営業の情報循環体制 | 架電状況・反応・次回の改善点を常時共有 |
| アポ後の即アクション設計 | 商談までのスピードを意識し、温度が高いうちに対応 |
自治体営業では、「一度つながったら即商談化」というケースは稀です。だからこそ、“つながった後の対応の質”が勝敗を分けます。本事例のように、アポ代行で扉を開け、営業が即座に中に入っていける体制を整えた企業こそ、成果を掴んでいます。
アポ代行は、ただの外注先ではなく、“自治体営業の突破口”をともに設計していくビジネスパートナーです。今回紹介した企業に共通していたのは、「アポを取るのは代行、売るのは自社」という分業ではなく、「一緒に営業するチーム」として動いていた点です。
この姿勢こそが、「つながらない」を突破し、継続的に自治体案件を受注できる体質を生み出していくのです。
まとめ
自治体営業における最大の壁は、「電話がつながらない」こと。そして、仮につながっても“適切な部署・担当者にたどり着けない”まま営業機会を逃してしまう企業が少なくありません。
自治体に強みを持つテレアポ代行サービス「タノメイト」は、そうした現場のリアルに応えるべく、専門オペレーターによる精度の高いアプローチで、商談へとつながるアポイントを創出します。自治体営業の成果を本気で高めたい企業様は、ぜひ一度 タノメイト公式サイト をご覧ください。成功の第一歩は、確実な“接点”から始まります。
👉 詳しくはこちら:タノメイト公式サイト

タノメイト編集部です。テレアポのプロの視点から、テレアポに関するさまざまな情報をわかりやすく発信します。
【タノメイトとは?】
タノメイトは「質の高いリード獲得」にこだわる、成果報酬型テレアポ代行サービスです。リード獲得にお悩みの企業様はぜひお問い合わせください。
商談につながるアポを獲得
完全成果報酬型テレアポ代行
『タノメイト』
● 初期費用・固定費0円
リードを獲得した分だけお支払い。完全成果報酬型でリスクゼロだから今すぐ始められます。
● 質の高いリード獲得
成功事例に基づくスクリプトと精度の高いリストを活用。質の高いリードを獲得します。
● 安心のキャンセル保証
条件をクリアしたリードのみご案内。条件を満たさないリードはキャンセル可能です。

\ リスクゼロで始めるテレアポ代行 /