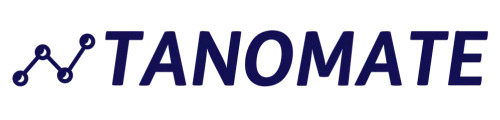決裁者と話せる営業へ!学校法人アプローチで成果を出す戦略とは
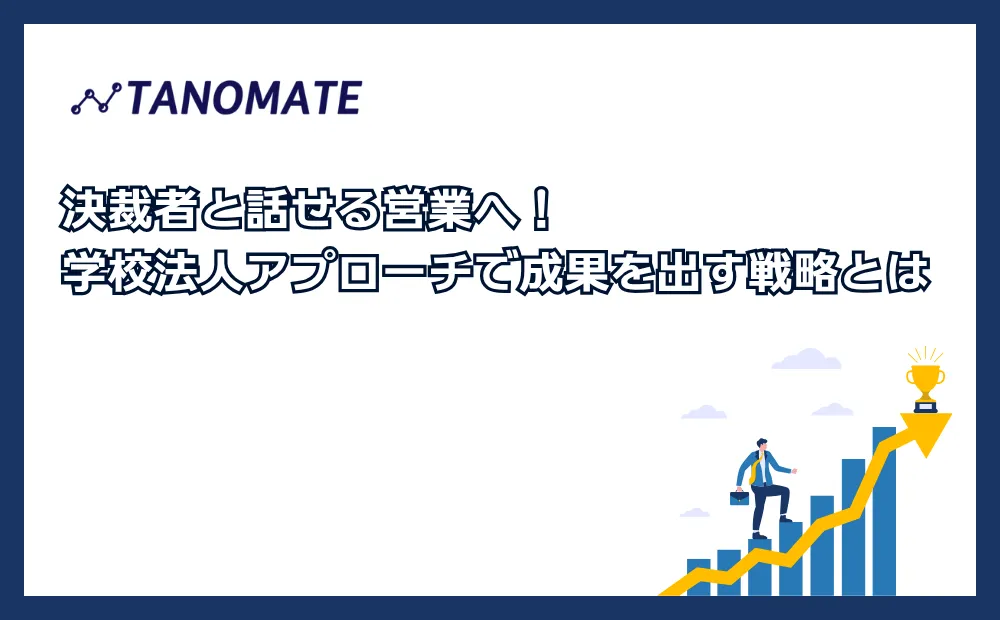
学校法人への営業活動において、「決裁者と直接対話できれば契約に至る可能性が高い」と感じながらも、その決裁者との接点を持つこと自体が難しいと悩む営業担当者は少なくありません。この課題の背景には、営業スキルの問題ではなく、教育機関特有の組織構造や意思決定プロセスへの理解不足、そして効果的なアプローチ方法の欠如が挙げられます。本コラムでは、教育機関の決裁者に効果的にリーチし、商談を成功に導くための戦略を体系的に解説します
- 1. なぜ“決裁者に届かない”のか?学校法人営業の構造的課題
- 1.1. 校長=決裁者とは限らない、複雑な意思決定フロー
- 1.2. 校務優先の現場で、“営業の話”は後回しにされる
- 1.3. 典型的な失敗パターン:「熱意は伝わっても、決裁者には届かない」
- 1.4. 「営業スキルの問題」ではなく、「構造理解と設計の問題」
- 2. 成果を出す企業が実践している“3つのアプローチ設計”とは
- 2.1. 【ターゲット設計】校種・課題ごとの役職を狙う
- 2.2. 【トーク設計】現場に“刺さる言葉”を用意している
- 2.3. 【タイミング設計】“話してもらえる時期”を狙っている
- 2.4. 構造を押さえた営業こそ、決裁者へ届く
- 3. “アポが取れる”だけでは足りない。商談につながる初回接点とは
- 3.1. 商談に進まないアポの共通点
- 3.2. 商談につながるアポに必要な3つの条件
- 3.3. スクリプトと話し方にも“現場配慮”を
- 3.4. アポ代行活用時も「商談化を見据えた設計」が重要
- 4. 初回接点をプロに任せる。「営業チームの一員」としてのアポ代行活用術
- 4.1. 架電を自社で抱え続ける非効率とリスク
- 4.2. アポ代行は“外注”ではなく“入口戦略の実行部隊”
- 4.3. 商談化率を上げるには、「役割分担」と「再現性」が必要
- 4.4. マネージャーが検討すべきは、「どこに人を割くか」
- 5. 営業を“届く仕組み”に変えるためのアクションチェックリスト
- 5.1. 誰に・何を・どう伝えるかの設計が“言語化”されているか?
- 5.2. アプローチするタイミングは戦略的に設計されているか?
- 5.3. 接点づくりと提案活動が分業されているか?
- 5.4. 決裁構造を前提としたリストが整っているか?
- 5.5. 「会えば決まる」営業を、仕組みで実現するために
- 6. まとめ
- 6.1. “会えば通る”のに、会えない営業を終わらせるために

目次
なぜ“決裁者に届かない”のか?学校法人営業の構造的課題
「教育機関 営業は難しい」。そう語る営業担当者は少なくありません。中でも多く聞かれるのが、「学校法人の決裁者にたどり着けない」という課題です。実際、どれだけ提案内容が魅力的でも、“届かない”提案はなかったことと同じ──営業の根本的な機能不全を引き起こします。
では、なぜ学校法人では「話すべき相手」にたどり着くのが難しいのでしょうか? その要因は、学校特有の意思決定構造と文化的な壁にあります。
校長=決裁者とは限らない、複雑な意思決定フロー
企業営業では、「役職=決裁者」であるケースが多く、相手の肩書きを見れば話の通し方がある程度読めます。しかし、学校法人営業では話が違います。
たとえば:
・ICT教材の導入:現場ニーズは教務主任→教頭が整理→校長が承認→理事会が決裁
・キャリア支援:進路指導部が検討→教頭を通して校長→最終的に教育委員会へ報告
このように、「誰が情報を取りまとめ、誰が判断し、誰がハンコを押すのか」が非常に見えづらいのが、学校法人 アプローチの難しさです。特に公立校では教育委員会の意向が強く影響する場合もあり、学校単体で完結しない意思決定も少なくありません。
校務優先の現場で、“営業の話”は後回しにされる
教育機関は「教育」が最優先。そのため、営業活動はどうしても後回しにされがちです。電話をかけても「担当が不在です」「お時間が取れません」で終わってしまうケースは日常茶飯事です。
さらに、学校側のスケジュールも変動が多く、行事・試験・委員会などで1日が埋まり、商談の調整が長引くこともしばしば。「今は忙しいので…」という断り文句が実質の“拒絶”となってしまうこともあります。
典型的な失敗パターン:「熱意は伝わっても、決裁者には届かない」
例えばこんなケースがあります。
ある営業担当者は、公立高校の進路指導主事と面談を5回重ね、丁寧に提案を進めていました。担当者も前向きで、導入の期待は高まっていた──ところが、実際には校長には一切話が通っておらず、決裁段階で突然「初耳です」と白紙に戻ってしまいました。これはまさに、「話すべき相手に届いていない」典型です。情報収集者や現場担当者とだけ話をしても、意思決定プロセスに食い込めなければ、いくら提案を磨いても結果にはつながりません。
「営業スキルの問題」ではなく、「構造理解と設計の問題」
このような背景から、学校法人営業で商談数を安定的に増やすには、「どう話すか」ではなく「誰に、どの順番で、どう届けるか」の構造設計が欠かせません。
教育機関 新規開拓を進める際に、営業手法やトークスキルだけに目を向けていては、成果が出にくいのは当然とも言えます。むしろ、営業活動の設計図を描くこと──それこそが“決裁者とつながる営業”の出発点なのです。
次章では、実際に成果を出している企業が実践している、「教育機関 営業 成功法」としてのアプローチ設計について解説していきます。
成果を出す企業が実践している“3つのアプローチ設計”とは
学校法人への営業で成果を出している企業には、共通する「アプローチ設計の型」があります。特別な営業スキルや潤沢な人員があるわけではありません。鍵となっているのは、初回接点から決裁者接触までのプロセスが「戦略的に設計されている」ことです。
ここでは、教育機関 営業で成果を出す企業が実践している3つの重要設計要素を紹介します。
【ターゲット設計】校種・課題ごとの役職を狙う
成果を出している企業は、「誰に話すか」ではなく「何の課題に誰が関与しているか」からターゲットを設定しています。たとえば、
・ICT教材の導入なら「教務主任→教頭→校長」
・キャリア支援商材なら「進路指導部→教頭→校長」
・健康、福祉系のサービスなら「養護教諭→管理職」ルートも有効
このように、校種(小中高・私立公立)や課題に応じて、主導権を持つポジションを見極めたターゲット設計がポイントです。
【トーク設計】現場に“刺さる言葉”を用意している
成果を出している企業は、初回の接点でも「教育現場が重視している観点」で語る工夫をしています。具体的には以下のようなキーワードが有効です。
「教育効果の可視化ができる教材です」
「先生の授業準備の負担を軽減できます」
「○○高校や△△中学校でもすでにご導入いただいています」
逆に、「コスト削減」「DX推進」など一般的なBtoBトークでは刺さりません。教育機関特有の価値観に即したトーク設計が、次のステップに進めるかどうかの分かれ目になります。
【タイミング設計】“話してもらえる時期”を狙っている
教育機関は、時期によって営業の反応率が大きく変動する特殊な市場です。
| 時期 | 状況 | アプローチ推奨度 |
|---|---|---|
| 4〜5月 | 新体制スタート。導入検討が始まる時期。 | ◎ |
| 6月中旬〜7月初旬 | 試験期間・進路指導などで多忙 | △ |
| 9月〜10月 | 文化祭など行事で埋まりやすい | △ |
| 11月下旬〜12月 | 翌年度準備の検討が本格化 | ◎ |
| 2月〜3月 | 期末業務・移動準備で最も忙しい | × |
このように、「営業したい時」ではなく、「相手が話せる時」に合わせた接触設計が、商談化率に直結します。
構造を押さえた営業こそ、決裁者へ届く
教育機関の新規開拓で成果を出している企業は、営業担当者の勘や経験に頼らず、再現性あるアプローチ設計を体系化しています。
「どう提案するか」よりも前に、「誰に・何を・いつ届けるか」の設計が整っているか。ここを磨き上げることが、学校法人 決裁者に届く営業戦略の土台となるのです。
次章では、こうした設計を実行に移す際に重要となる「初回接点のつくり方」と、アポ代行を活用した効率的なアプローチ手法について詳しく解説します。
“アポが取れる”だけでは足りない。商談につながる初回接点とは
教育機関 営業では、「アポが取れた=成果に近づいた」とは限りません。実際には、“とりあえず取ったアポ”が空振りに終わるケースも多く見られます。
その背景にあるのは、初回接点の設計不足です。誰と・どんな目的で・何を話すのかが曖昧なまま進めてしまうと、相手にとっては「なんとなく聞いた話」で終わってしまいます。
商談に進まないアポの共通点
とりわけ学校法人 アプローチでは、以下のような初回接点が失敗を招きがちです。
・対象者の選定ミス:「情報収集を担当しているだけの職員」との面談
・目的の不明瞭さ:「ご挨拶だけでも」「資料だけでも見てください」といった曖昧な依頼
・価値の伝達不足:「自社の説明」に終始してしまい、教育現場の課題に寄り添えていない
このようなケースでは、アポは成立しても、次に繋がる会話にならず、決裁者に届く前に商談が失速してしまいます。
商談につながるアポに必要な3つの条件
成果を出している企業は、初回接点において以下3点を明確にしています。
1.「誰と話すか」:決裁者に近いポジションをターゲットに
例:ICT教材 → 教務主任または教頭、キャリア支援 → 進路指導主事
2.「どんな目的か」:単なる説明ではなく“検討の入り口”であると伝える
例:「新年度の授業設計に関連してご提案したい内容がございます」
3.「何を話すか」:教育現場が価値を感じる情報を提示
例:「他校での活用事例」「学習成果の可視化」「先生方の業務軽減実績」
これらが揃って初めて、教育機関との商談数を安定的に生み出す接点設計となります。
スクリプトと話し方にも“現場配慮”を
教育機関営業での架電トークでは、“言葉選び”が成果を分けます。以下にNG・OKの例を挙げます。
| NGトーク例 | OKトーク例 |
|---|---|
| 「〇〇の営業でお電話しました」 | 「教務のご担当者様に、業務軽減のご提案でのご連絡です」 |
| 「一度お話だけでも」 | 「実際の導入校で効果が出ている事例を紹介できます」 |
| 「送付資料だけでも可能でしょうか」 | 「御校にに関する具体事例を添えてお送り可能です」 |
“営業されている”と感じさせず、“参考になる話”として自然に会話を始めることがカギです。
アポ代行活用時も「商談化を見据えた設計」が重要
アポ代行 教育業界を活用する際も、単に件数を追うのではなく、“商談に進むための接点づくり”を重視できるかが重要な選定基準です。
トークスクリプトやターゲット設計が曖昧なままでは、代行を使っても商談化率は上がりません。
教育機関へのアポ取り方の精度を見直すことで、営業の成果は大きく変わります。次章では、「提案に集中できる体制づくり」として、アポ代行をどう位置づけるかを詳しく解説します。
初回接点をプロに任せる。「営業チームの一員」としてのアポ代行活用術
教育機関への営業において、最も工数がかかり、成果につながりづらいのが「初回接点の創出」です。電話が通じない、タイミングが合わない、決裁者が誰か分からない──こうした壁に、貴重な営業リソースが割かれていませんか?
成果を出している営業マネージャーは、営業チームを「提案に専念させる体制」づくりに動いています。その鍵となるのが、「初回接点をプロに任せる」という判断です。
架電を自社で抱え続ける非効率とリスク
たとえば、1日50件架電して2件話せるかどうか。決裁者ではない職員に断られることも多く、1件の有効アポを得るために1営業日かかるケースもあります。
結果として、提案準備やクロージングといった「受注に直結する業務」へリソースを割けなくなってしまう。
このような状態が続くと、チームのモチベーションも下がり、営業全体の生産性が落ち込む原因になります。
アポ代行は“外注”ではなく“入口戦略の実行部隊”
アポ代行を「外注業者」として扱うと、成果も“件数”止まりになりがちです。しかし、営業成果を出している企業は、アポ代行を「営業戦略の一部を担う実働部隊」として活用しています。
たとえばタノメイトでは、ただアポを取るのではなく、以下のような業務を営業チームと並走しながら実行します。
◆タノメイトの営業設計支援(例)
| 項目 | 実施内容例 |
|---|---|
| ターゲット設計 | 校種ごとの課題から、担当者を抽出(教務主任、進路指導部、教頭) |
| トーク設計 | 「教育効果が出る」「業務が軽くなる」「他校導入実績あり」など、教育現場に刺さる表現を設計 |
| タイミング設計 | 行事カレンダーや年度スケジュールをもとに、架電NG時期・推奨時期を精査 |
| ヒアリング情報 | 架電時に得た、現場のリアルな声をレポート化し、営業チームの提案資料に反映 |
このように、単なる“アポ数”ではなく、“商談化につながる接点”を設計から実行まで支援するのが、タノメイトの強みです。
商談化率を上げるには、「役割分担」と「再現性」が必要
営業担当者が一人でアポも提案もクロージングも対応するスタイルは、属人化しやすく、成果がブレやすくなります。
一方、初回接点を専門チームが創出し、営業チームが“商談に集中する”体制を取ることで、成果の再現性が飛躍的に高まるのです。
マネージャーが検討すべきは、「どこに人を割くか」
営業マネージャーにとって最も重要なのは、「どこに人と時間をかけるべきか」の設計です。アポ取得は重要ですが、商談の質と数を高める“入口設計”はプロに任せるという判断が、チーム全体の成果を底上げします。
もし、
「営業が忙しすぎて新規が回せていない」
「初回接点が属人化していて再現できない」
と感じているなら、今こそアポ代行を“営業チームの一員”として迎える時かもしれません。
営業を“届く仕組み”に変えるためのアクションチェックリスト
「決裁者と話せれば通る」。これは多くの教育機関向け営業担当が口にする実感です。にもかかわらず、商談数が伸びないのは、営業担当者のスキルや努力ではなく、“仕組み”が整っていないことに原因がある場合がほとんどです。
本章では、教育機関への営業活動を再現性ある成果に変えるためのアクションチェックリストをご紹介します。
誰に・何を・どう伝えるかの設計が“言語化”されているか?
「誰に話すか」を個人の勘に頼っていませんか?
商材別・校種別に「話すべき役職」と「伝えるべき価値」を事前に明文化し、トークスクリプトに反映できていなければ、接点が偶発的になります。
たとえば:
・ICT教材 → 教務主任/教頭/校長への順序立て
・キャリア系サービス → 進路指導部→教頭→校長・事務長ライン
こうしたルートが見えていれば、初回接点から“決裁者に届く営業”に変わります。
アプローチするタイミングは戦略的に設計されているか?
教育機関の年間スケジュールは特殊です。提案の反応率は、内容以上に“タイミング”で大きく変わります。
4月:新年度準備で比較的余裕あり(◎)
7月:定期試験・終業式などで商談どころではない(×)
10月:文化祭・外部対応など行事が重なる(△)
11月:次年度の検討が始まり、導入を考える時期(◎)
こうした“営業できる時期”のナレッジが共有・活用されているかが、教育機関との商談数の安定化に直結します。
接点づくりと提案活動が分業されているか?
教育機関への営業において、アポ取得と商談準備・提案は別スキル領域です。初回接点づくりは、教育的配慮のある話法や電話タイミングのノウハウが必要であり、営業が自ら抱え込むと非効率です。
・営業担当は「行けば決まる」相手に集中
・初回接点はアポ代行などの外部パートナーが創出
このような“分業体制”の導入で、1人あたりの営業生産性は大きく向上します。
決裁構造を前提としたリストが整っているか?
学校法人は、企業とは異なり「役職=決裁者」ではないことが多く、構造理解が不十分なリストでは空回りが起きます。
・情報収集者に5回説明 → 決裁者未接触で白紙に
・本来は教育委員会が決裁する案件に、学校長アプローチだけで完了を目指す
このようなケースを防ぐためには、「誰がどう判断し、誰が意思決定に関与するか」というフローを前提としたターゲット設計が不可欠です。
「会えば決まる」営業を、仕組みで実現するために
教育機関営業は「つながれば可能性がある」市場です。しかし、構造を理解せず、行き当たりばったりの営業をしていては成果は出ません。
属人的な勘や偶然に頼らず、「誰に・何を・いつ・どう届けるか」を見える化し、接点づくりを仕組みとして組み込む。それが、決裁者に届く営業、そして成果につながる営業の最短ルートです。
まとめ
“会えば通る”のに、会えない営業を終わらせるために
教育機関への営業は、提案内容やサービスの質だけで成果が決まるものではありません。最大の課題は、「話したい相手に、まず“会う”ことができない」という構造的な壁にあります。
この“初回接点の不在”こそが、商談数の伸び悩みや決裁者に届かない原因の本質です。
タノメイトは、教育業界にアポ獲得強みを持つプロフェッショナルとして、接点設計・スクリプト・タイミングまでを含めた“届くアプローチ”をご提供しています。
「提案に集中したい」「初回接点の精度を上げたい」
そうお考えの営業マネージャーの皆さまへ──
まずは、タノメイトの支援内容をご覧ください。商談につながる第一歩は、“アポ”の質から変えられます。
👉 詳しくはこちら:https://tanomate.net/

タノメイト編集部です。テレアポのプロの視点から、テレアポに関するさまざまな情報をわかりやすく発信します。
【タノメイトとは?】
タノメイトは「質の高いリード獲得」にこだわる、成果報酬型テレアポ代行サービスです。リード獲得にお悩みの企業様はぜひお問い合わせください。
商談につながるアポを獲得
完全成果報酬型テレアポ代行
『タノメイト』
● 初期費用・固定費0円
リードを獲得した分だけお支払い。完全成果報酬型でリスクゼロだから今すぐ始められます。
● 質の高いリード獲得
成功事例に基づくスクリプトと精度の高いリストを活用。質の高いリードを獲得します。
● 安心のキャンセル保証
条件をクリアしたリードのみご案内。条件を満たさないリードはキャンセル可能です。

\ リスクゼロで始めるテレアポ代行 /