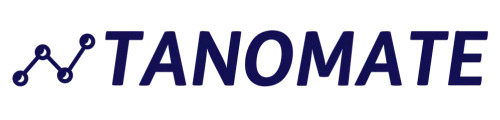なぜ自治体営業は難しいのか?アポ代行で成果を出す企業の共通点
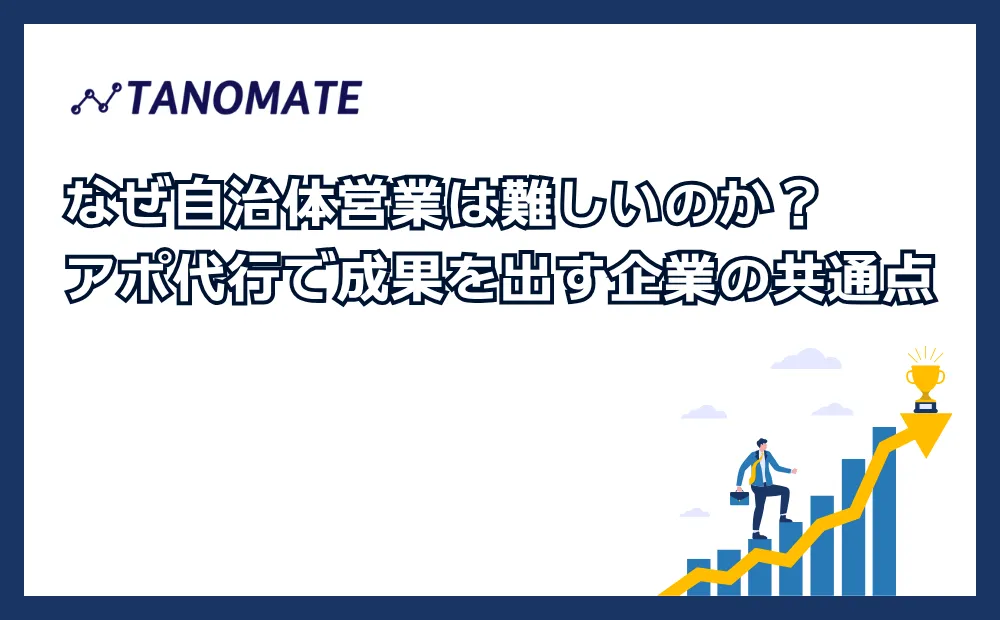
営業のプロでも苦戦する──それが「自治体営業」です。
「自治体に営業をかけたいが、担当者にまったくつながらない…」
「メールやFAXを送っても音沙汰がない…」
「入札や公募以外でどうアプローチすればいいのか分からない…」
そんな悩みを抱える事業者は、業種を問わず少なくありません。
自治体営業は、民間企業向けとは異なる“独特のルールと文化”が存在する領域です。長期的な関係構築が求められ、部署構造や決裁フローも複雑。さらに、営業活動の初動となる「担当者との接点づくり」が、極めて難しいのが特徴です。
そこで注目されているのが、テレアポ代行(アポ代行)という選択肢。
営業リソースに限りがある企業でも、アポ代行をうまく活用することで、これまで届かなかった自治体の“中”へと確実に踏み込めるようになってきています。
本コラムでは、
・自治体営業がなぜ難しいのか?
・アポ代行を使って成果を出している企業の共通点とは?
・自治体営業におけるアポ代行の実践的な活用法とは?
という視点から、自治体営業の壁を乗り越えるための具体策を、営業経験者向けに深掘りしていきます。
本稿が営業戦略の見直しとアップデートの一助になれば幸いです。
- 1. なぜ自治体営業は難しいのか?
- 1.1. 担当者にたどり着くまでが最大のハードル
- 1.2. 意思決定の遅さと、稟議の複雑さ
- 1.3. 差別化が効きづらく、実績・信頼が求められる世界
- 1.4. 入札や公募だけでは、継続的な案件につながらない
- 1.5. 難しさの本質は「入口の不在」と「営業設計のズレ」
- 2. 自治体営業に失敗しがちな企業の特徴
- 2.1. 行政文化と意思決定の“文脈”を理解していない
- 2.2. 決裁者・キーマンにアクセスできていない
- 2.3. 提案が“民間目線”に寄りすぎている
- 2.4. 失敗しないためには、“行政文脈”を設計に組み込むことが不可欠
- 3. なぜアポ代行が自治体営業で効果を発揮するのか?
- 3.1. 担当者特定という“最難関”を突破できる
- 3.2. 架電データの蓄積が、営業を“再現可能”にする
- 3.3. 行政に響く“キラートーク”を設計できる
- 3.4. “つながらない問題”を仕組みで乗り越える
- 3.5. 社内リソースを最適配分し、営業全体を底上げする
- 3.6. アポ代行は「戦略的インサイドセールスパートナー」
- 4. アポ代行で成果を上げている企業の共通点
- 4.1. “民間用”の言葉を“自治体語”に翻訳している
- 4.2. アポ代行と“チーム営業”ができている
- 4.3. “短期決戦”ではなく“年度をまたぐ長期設計”が前提
- 4.4. “印象で終わらない資料”と“聞き出す設計”を持っている
- 4.5. “取って終わり”にせず、常に改善を回している
- 5. 自治体営業で成果を出すために、アポ代行とどう連携すべきか?
- 5.1. 情報共有は「精度×深度」が鍵
- 5.2. トークスクリプトは“自社+代行の共創”で組み立てる
- 5.3. 架電結果を“営業資産”として活用するフィードバック体制
- 5.4. 役割分担を明確にした“分業設計”が成果を左右する
- 6. まとめ
- 6.1. 自治体営業の“入口設計”でお悩みなら、まずはタノメイトへ

目次
なぜ自治体営業は難しいのか?
民間企業との取引経験が豊富な営業担当者であっても、「自治体営業は勝手が違う」と戸惑う場面は少なくありません。
実際に、当社にも「代表電話は何度かけても取り次いでもらえない」「そもそも誰が担当なのか分からない」「いい提案だと思ってもらえても、なかなか前に進まない」といった相談が多く寄せられています。
このような壁に直面するのは、個別の企業努力の問題というよりも、自治体という組織の性質上、営業活動そのものが“構造的に難しい”ものになっているからです。
担当者にたどり着くまでが最大のハードル
自治体営業でまず直面するのが、「誰にアプローチすればいいのか分からない」という問題です。自治体の組織体制は縦割りかつ細分化されており、部署名も統一されていないことが多いため、自社の提案がどの担当に響くのかを見極めるだけでも一苦労です。
さらに、代表電話から担当部署につないでもらうことは簡単ではありません。個人名や直通番号が公開されていないのはもちろん、「お繋ぎできません」「担当者は不在です」といった応対も少なくありません。民間企業であれば当たり前に行える“キーマンへの接触”が、自治体では「まず会話のスタートラインに立つこと自体が難しい」のです。
意思決定の遅さと、稟議の複雑さ
仮に担当者と接触できたとしても、すぐに商談に発展するとは限りません。
自治体では、ひとつの案件に対して複数の部署や職層が関与し、合議や稟議を経て意思決定がなされるケースがほとんどです。担当者が「導入したい」と思っても、そこから予算部門、財政課、そして最終的には議会にまで話が上がることもあり、民間のように“1対1”で完結する意思決定構造ではないのです。
また、提案が通るかどうかは“タイミング”にも大きく左右されます。
多くの自治体では、予算編成や決裁スケジュールが年度単位で動いているため、良い提案であっても「今年度は難しい」「来年度で検討します」となることも日常茶飯事です。一度の接点で案件化を狙うのではなく、複数年度をまたいで“仕込み続ける”姿勢が求められるのが実情です。
差別化が効きづらく、実績・信頼が求められる世界
自治体では、民間のように「面白い」「斬新だ」といった要素だけで導入が決まることはありません。むしろ、重要視されるのは前例や公共性、そして提供企業への信頼感です。
提案内容が優れていたとしても、「自治体での導入実績がない」「知名度が低い」といった理由で慎重な対応を取られることは珍しくありません。
さらに、自治体では公平性・中立性を保つために、特定の企業を“特別扱いすること”自体に抵抗がある文化も存在します。
そのため、他社との差別化を打ち出すには、「製品のスペック」だけでなく、「行政課題との接点」「住民サービスへの波及効果」「費用対効果」「継続的な運用サポート体制」など、自治体が重視する観点での提案設計が不可欠になります。
入札や公募だけでは、継続的な案件につながらない
「公募案件で一度受注したが、その後が続かない」
そんな悩みを抱える企業も少なくありません。
自治体との関係構築がうまくできていないまま入札や公募に頼ると、単発受注で終わってしまい、再提案やリピート発注にはつながらないのです。
自治体営業においては、予算要求の段階から情報提供できる関係性を築いておくことが鍵になります。つまり、案件化のずっと前から「この企業なら相談できそうだ」と思ってもらえる存在になること。
そのためには、定期的な情報提供や、接点の継続が不可欠です。
難しさの本質は「入口の不在」と「営業設計のズレ」
自治体営業が難しい最大の理由は、“誰に・どう届けるか”という導線設計が最初から存在しないことです。民間営業の常識では通用しないため、従来の営業戦略をそのまま踏襲しても成果にはつながりません。
求められるのは、以下のような戦略的アプローチです。
・自治体特有の意思決定構造を前提とした営業設計
・部署ごとの関心領域・業務領域を理解したターゲティング
・長期視点での情報接点の構築と、案件化までの並走体制
そして、この“最初の接点”をつくる手段として、自治体営業に強みを持つアポ代行の活用が今、注目されています。
自治体営業に失敗しがちな企業の特徴
自治体営業に取り組んでいる企業の中には、「一度提案したが、それっきり音沙汰がない」「熱心に説明したのに、最終的に“予算の関係で”と断られた」といった経験を持つケースが少なくありません。
こうした失敗には、いくつかの典型的な落とし穴が存在します。ここでは、特に見落とされがちな4つの特徴に焦点を当てて解説します。
行政文化と意思決定の“文脈”を理解していない
民間企業のスピード感や意思決定の単独性に慣れていると、自治体特有の合議・稟議文化や前例主義を「非効率」と見なしてしまいがちです。
しかし、自治体では「過去に導入されたか」「他自治体での実績があるか」といった点が、提案の受け入れ可否に直結します。
行政組織は“慎重であること”を前提に設計された仕組みです。
この価値観を踏まえずに、「コスト削減になります」「最新技術です」と一方的に訴求しても、相手の心理的バリアは崩せません。
決裁者・キーマンにアクセスできていない
「提案内容には一定の関心を示してもらえたのに、その後につながらなかった」
この背景には、“決裁者に届いていない”という根本的な問題があります。
担当者が前向きな姿勢を示してくれたとしても、それだけで商談が前に進むことは稀です。自治体では、複数の階層を経由した決裁プロセスが一般的であり、最終的な判断権を持つ人物に直接届くかどうかが極めて重要です。
担当者:「上にも相談してみます」
↓
数週間後:「今回は見送ることになりました」
↓
(実はそもそも“上”にまで話が上がっていない)
このようなケースは非常に多く、アプローチの起点が間違っていたことで、チャンスを逃してしまっているのです。
提案が“民間目線”に寄りすぎている
「今が営業の空き時間だから」といった社内事情でアプローチしてしまうと、自治体の予算サイクルとズレてしまい、すぐには案件化できないという結果に終わることがほとんどです。
多くの自治体では、
・7〜9月:次年度の予算要求の準備
・10〜12月:予算案の確定と査定
・1〜3月:年度末業務で超繁忙期
という流れで動いており、「いつ・誰に・何を届けるか」の精度が重要です。
年度の後半に「来年度の予算に入れてほしい」と提案しても、実はもう予算編成が終わっていた、というのは非常に多い失敗パターンです。
失敗しないためには、“行政文脈”を設計に組み込むことが不可欠
自治体営業で成果が出ない企業の多くは、「自社が売りたいこと」を優先するあまり、自治体側の時間軸・価値観・役職構造を見落としている傾向にあります。自治体営業では、営業そのものを「行政に合わせた文脈と設計に再構築する」ことが求められます。
次章では、こうした構造的な課題に対して、アポ代行がどのように突破口となり得るのかを、具体的に紐解いていきます。
なぜアポ代行が自治体営業で効果を発揮するのか?
自治体営業は、サービスや製品の優位性だけでは突破できません。
最初の接点、つまり「担当者に“きちんと届くか”どうか」で勝負が決まる場面が非常に多く、そこを担保できない限り、どんなに素晴らしい提案も“知られずに終わる”のが実情です。
このような課題を背景に、営業活動の“入口設計”を専門的に担う手段として、アポ代行が強く機能するケースが増えています。ここでは、なぜアポ代行が自治体営業において効果を発揮するのか、その根拠を5つの視点から解説します。
担当者特定という“最難関”を突破できる
自治体営業において、最大のボトルネックは「誰に提案すべきかが分からない」こと。部署名が不統一、所掌業務が複雑、加えて人事異動が頻繁となれば、適切な担当者にたどり着くこと自体が至難の業です。
アポ代行会社は、この“初動の壁”を超えるために、過去の架電ナレッジや組織図の経験的理解を武器に、短期間で担当者を割り出します。
たとえば「防災関連だから危機管理課だと思ったら、実際には総務課の傘下にある防災安全係が担当だった」といったケースも即座に対応可能です。
✅ “繋ぐ先”の精度が高い。それだけで商談率は大きく変わるのです。
架電データの蓄積が、営業を“再現可能”にする
アポ代行の強みは、単なるテレアポ実行ではなく、日々の架電履歴を構造化・データベース化していることにあります。
・どの自治体で誰が応じたか
・どういうトークが刺さったか
・どのタイミングが繋がりやすかったか
これらはすべて、次の案件の“成功確率を高める材料”となります。
しかも、属人的ではなく、蓄積されたナレッジとして営業活動全体に活かせるのが、アウトバウンド型の営業代行とは一線を画すポイントです。
行政に響く“キラートーク”を設計できる
自治体営業では、「何を話すか」以上に「どう話すか、どの文脈で伝えるか」が問われます。民間企業では通用する「コスト削減」「効率化」といったキーワードも、自治体にとっては「予算が減ることで住民サービスが削られるのでは?」という誤解につながる可能性があります。
アポ代行は、自治体特有の言語感覚と価値判断軸に最適化したトークスクリプトを用意。「市民満足度」「業務負荷軽減」「自治体間格差の是正」といった切り口で、職員が“説明責任を果たしやすい”提案文脈を先回りして提示することが可能です。
✅ 目的は、アポを取ることではなく、“次に進める”アポを取ること。
“つながらない問題”を仕組みで乗り越える
「3回電話したが不在」「何度かけても事務局止まり」――これは多くの営業担当者が抱える現実です。自治体営業では、1回の不在=失注ではなく、数十回に及ぶ試行錯誤が前提の活動になります。
アポ代行は、“繋がらない前提”の中で、架電スケジュール・部署連携・複数ルートでの確認など、社内では実行が難しい粘り強いアプローチを継続的に運用できる体制を持っています。
「繋がるまでやり切る仕組み」があるからこそ、商談機会の母数が劇的に変わるのです。
社内リソースを最適配分し、営業全体を底上げする
自治体営業に取り組む企業の多くが抱える課題のひとつに、「人手不足と優先順位の低下」があります。民間営業の即効性が重視されがちな中、自治体向けアプローチはつい後回しにされてしまい、案件化までの導線が断絶してしまうのです。
アポ代行を活用すれば、初動の“つながるまで”を外部化することで、フィールド営業は“つながった後”に集中できる体制が整います。営業効率が向上するだけでなく、自治体営業に継続的に投資できる組織力を築くことにもつながります。
アポ代行は「戦略的インサイドセールスパートナー」
単なるテレアポ代行ではなく、自治体営業における“入口設計”と“組織知の活用”を担う存在――それがアポ代行の本質です。
・誰に、どのように届けるかを設計し
・届けるための行動を継続的に行い
・蓄積された知見を次のアプローチに反映する
こうした再現可能な営業プロセスを確立できるかどうかが、自治体営業の成果を左右する要因となっています。
次章では、アポ代行を活用して実際に成果を出している企業が、どのような営業体制を築いているのか、その共通点を掘り下げていきます。
アポ代行で成果を上げている企業の共通点
アポ代行を活用して自治体営業で成果を出している企業には、明確な共通項があります。単に「アポイントを外注している」のではなく、営業の構造そのものを自治体仕様に変換し、アポ代行を“戦略パートナー”として組み込んでいる点に特徴があります。ここでは、実際の支援現場で見えてきた“勝てる企業の営業設計”を5つの視点から掘り下げます。
“民間用”の言葉を“自治体語”に翻訳している
成果を出している企業に共通しているのは、自社サービスの特徴を「自治体にとっての価値」に言い換える力を持っている点です。
たとえば、「業務効率化」が主軸のクラウドサービスであれば、
民間向けには「業務時間を40%削減」などの訴求をしますが、自治体向けにはそれを次のように言い換えます。
「職員1人あたり月20時間分の住民対応リソースを創出」
「住民満足度や“説明責任”の強化につながる業務設計」
“誰の、何の、どんな課題を、どのように改善するのか”を自治体の行政文脈で語れるかどうかが、商談の成否を大きく左右します。
アポ代行と“チーム営業”ができている
成果を出している企業は、アポ代行を「外注」ではなく「外部の営業チーム」として扱っているのが特徴です。
そのため、以下のようなやりとりが定例的に行われています。
・事前に対象自治体の「事業計画」「重点施策」などを共有
・営業トークは「民間寄り→自治体文脈」へ共同でチューニング
・アポ後のヒアリング内容も定型化し、商談資料に反映
架電担当と営業担当が「自治体の課題を共有する共通言語」を持って動いているため、1件1件のアポイントが“次につながる商談”へと転換されていくのです。
“短期決戦”ではなく“年度をまたぐ長期設計”が前提
自治体営業は、年度サイクル・予算編成・意思決定構造を理解した長期型アプローチが必要不可欠です。成果を出す企業は、「年度内にどうにかする」のではなく、来年度の予算要求に乗せるために、今期中に課題認識を共有するという営業戦略を描いています。
このように、「アポが取れた=すぐ案件化」ではなく、「今は火がつかなくても、次の波に向けて仕込む」という設計思想を持っているかどうかが、継続案件の蓄積を左右します。
“印象で終わらない資料”と“聞き出す設計”を持っている
アポ後の資料が“自治体向けに最適化”されているかどうかは、成果を左右する分水嶺です。成果を出している企業の資料には、共通して次のような特徴があります。
・他自治体での導入効果が定量データで明記されている
・「住民サービス」「行政負担」「地域課題」の文脈が盛り込まれている
・説明責任を果たしやすいように、意思決定フローを補助する構成
また、ヒアリング項目も“企業目線”ではなく、自治体の年度課題や計画策定スケジュールに即した設問設計がなされており、営業トークの深度が自然と深まり、次回提案への布石を打つことができるようになっています。
“取って終わり”にせず、常に改善を回している
成果を上げる企業は、アポを「点」ではなく「線」でとらえています。つまり、アポの質・内容・商談化率を数値と感覚で捉えながら、PDCAを継続しているのです。
✔️ どの自治体で反応が良かったか?
✔️ どのトーク・資料が突破口になったか?
✔️ 提案の温度感をどう引き上げたか?
こうしたフィードバックは、アポ代行と共有・改善され、トークスクリプトやターゲット選定が“データドリブンで進化”していきます。
✅ 成功の鍵は、「自治体営業に合わせて“仕組みを変える”覚悟」
アポ代行で成果を出す企業は、いずれも営業活動そのものを“自治体営業仕様”に再設計していることが共通しています。
①言葉を変え
②営業資料を変え
③アプローチのタイミングを変え
④フィードバックの運用体制を変える
その中心で、アポ代行を情報共有と実行力のハブとして活用しているのです。
テレアポ代行は“手段”であり、使い方次第で「接触率を上げるツール」にも「商談率を高める装置」にもなり得ます。
自治体営業で成果を出すために、アポ代行とどう連携すべきか?
アポ代行は「アポイント獲得の外注先」ではなく、“営業戦略の実行パートナー”として連携することで真価を発揮します。特に自治体営業では、ターゲット選定・トーク設計・情報共有のすべてを自治体特有の文脈に沿って構築する必要があるため、代行会社との密な連携設計が不可欠です。
この章では、実際に成果を出している企業が実践しているアポ代行との連携ノウハウを4つの観点からご紹介します。
情報共有は「精度×深度」が鍵
自治体営業では、単に「○○市にアポをとってほしい」では精度の高い営業は成立しません。成果を出している企業は、アポ代行と以下のような情報を初期段階でしっかり共有しています。
| 情報項目 | 共有のポイント例 |
|---|---|
| 対象自治体の選定 | 重点施策、財政状況、人口規模などの背景情報 |
| 想定部署・担当 | 過去案件、事業計画、業務所掌をベースに仮説を立てて提示 |
| 提案資料 | 自治体向けに最適化されたトーン・構成。導入効果や行政的メリットを明示 |
| 想定Q&A | よくある懸念(予算・公平性・業務負担)異対する解答例をセットで共有 |
この情報の“粒度”が細かいほど、アポの質と商談率が高まります。
トークスクリプトは“自社+代行の共創”で組み立てる
トークスクリプトは、アポ代行が独自に作るのではなく、クライアントと共同で設計するのが理想的です。なぜなら、自治体営業におけるファーストトークは、「提案そのもの」ではなく「担当者に届くかどうか」が重要な勝負所だからです。
たとえば以下のような構成が有効です:
冒頭:その自治体の施策や課題を踏まえた導入部(例:「貴自治体で取り組まれている○○推進計画に関連して…」)
中盤:提案概要と導入効果の“端的な整理”
終盤:ヒアリングの意図と“行政目線での対話姿勢”を明示
誰に・何を・どのように伝えるかを双方で細かくすり合わせることで、形式的な電話ではなく、次につながる“意義のあるアポ”が実現します。
架電結果を“営業資産”として活用するフィードバック体制
自治体営業では、電話がつながらなかった/断られたという結果も、戦略的な営業資産になり得ます。成果を出す企業は、アポ代行から以下のような情報を吸い上げ、営業全体の精度を高めています。
| フィードバックの項目 | 活用例 |
|---|---|
| 架電日時・対応者・対応内容 | アポ化率の高い時間帯の把握/キーマン選定のヒントに |
| 拒否理由 | 想定Q&A・資料表現・トーク改善のベースとなる |
| 関心度やリアクション | 次回提案タイミング/温度感分類による優先順位付け |
さらに、週1回〜月1回程度の定例ミーティングを設けてデータをレビューすることで、「アポの質」→「商談化率」→「受注率」までを意識した営業のPDCAループが構築されます。
役割分担を明確にした“分業設計”が成果を左右する
アポ代行を活用して成果を出している企業は、営業プロセス全体を“戦略的に分業化”しています。特に自治体営業では、次のような役割分担が効果的です。
| プロセス | 担当 |
|---|---|
| 初回接点構築 | アポ代行(架電・導入トーク・担当者特定) |
| 深掘りヒアリング | 自社営業(専門知識による課題ヒアリング) |
| 提案・受注 | 自社営業(提案資料作成・議会資料対応など) |
「誰が、どこまでを、どの質で行うか」を明確にすることで、アポ代行の力を最大限に引き出せる体制が完成します。
✅ “連携の質”が“成果の質”を決める
自治体営業において、アポ代行を単なる外注先と捉えるか、パートナーとして迎え入れるかで成果は大きく変わります。情報を開示し、トークを設計し、結果を分析し、営業プロセスを最適化していく。この一連の取り組みの中で、アポ代行は「商談の入口」を超えた戦略資産となっていくのです。
まとめ
自治体営業の“入口設計”でお悩みなら、まずはタノメイトへ
自治体営業で成果を出すには、「誰に・どう届けるか」という初動設計の精度がすべてを左右します。
私たちタノメイトは、自治体強化型のテレアポ代行として、担当者特定・トークスクリプト設計・PDCA運用までを一貫支援し、成果につながる“仕組みあるアポ獲得”を実現してきました。
❝もう自治体営業で遠回りしたくない❞
❝確度の高い自治体アポを、戦略的に取りたい❞
そんな方は、ぜひ一度、タノメイトの導入をご検討ください。
▶︎ タノメイト サービス詳細はこちら

タノメイト編集部です。テレアポのプロの視点から、テレアポに関するさまざまな情報をわかりやすく発信します。
【タノメイトとは?】
タノメイトは「質の高いリード獲得」にこだわる、成果報酬型テレアポ代行サービスです。リード獲得にお悩みの企業様はぜひお問い合わせください。
商談につながるアポを獲得
完全成果報酬型テレアポ代行
『タノメイト』
● 初期費用・固定費0円
リードを獲得した分だけお支払い。完全成果報酬型でリスクゼロだから今すぐ始められます。
● 質の高いリード獲得
成功事例に基づくスクリプトと精度の高いリストを活用。質の高いリードを獲得します。
● 安心のキャンセル保証
条件をクリアしたリードのみご案内。条件を満たさないリードはキャンセル可能です。

\ リスクゼロで始めるテレアポ代行 /