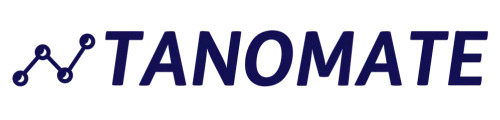自治体営業は“アポ次第”で動き出す!成果を生む営業アプローチの実践法
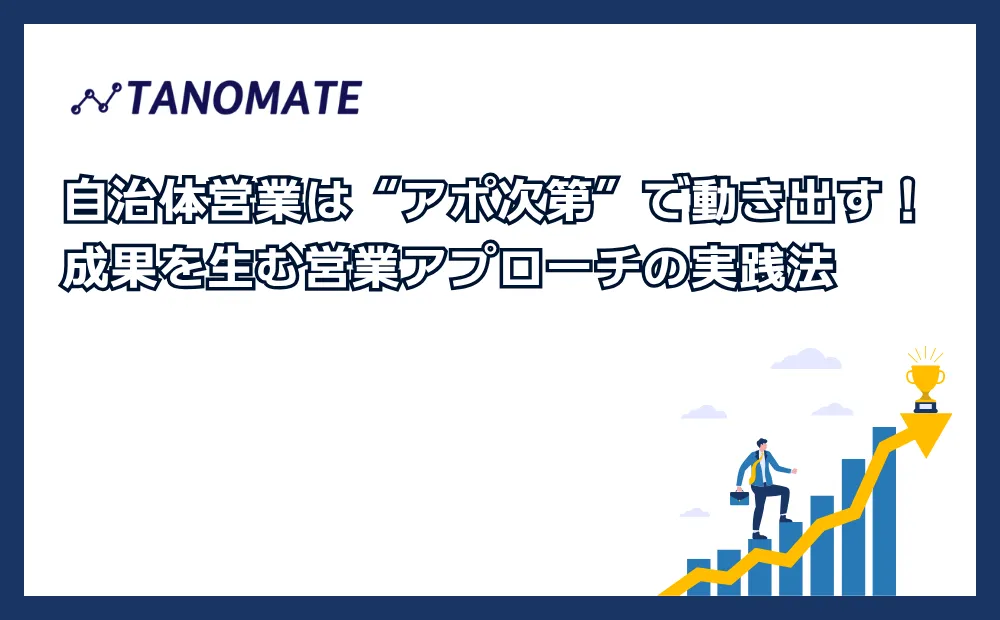
「自治体営業が思ったより進まない」「提案内容は悪くないはずなのに、そもそも商談にたどり着けない」――
こうした悩みを抱える企業は少なくありません。実際、どれほど優れたサービスやソリューションを持っていても、自治体との接点=アポが取れなければ、営業活動はスタートラインにすら立てないのが現実です。
民間営業と異なり、自治体営業では担当部署へのアクセスが困難であり、意思決定の構造も複雑。だからこそ、「誰に」「どんなタイミングで」「どう話しかけるか」というアポ設計の巧拙が、成果を大きく左右します。
本コラムでは、自治体営業における“成果につながるアポの取り方”をテーマに、接点構築の考え方や実践手法、さらにはアポ代行を活用した効率的な営業戦略について、実務に即した視点で解説していきます。
- 1. なぜ自治体営業は“アポが取れない”のか?
- 1.1. 代表電話・部署経由では“担当者にたどり着けない”
- 1.2. 業務所掌の構造が複雑で、誰に届ければいいのかが不明瞭
- 1.3. 異動が頻繁で、“人脈”が資産になりづらい
- 1.4. 営業を受け入れる文化が民間より防衛的
- 2. アポを取れても「案件化しない営業」が陥る3つの落とし穴
- 2.1. 話す相手がズレている
- 2.2. トークや資料が“民間感覚”のまま:行政文脈への翻訳不足
- 2.3. フォローがなく“一回きり”:継続的な信頼構築が欠如している
- 3. 成果につながる“自治体営業のアポ設計”とは
- 3.1. 信頼され、動かすアポには「戦略の設計図」がある
- 3.2. ターゲット部署と課題テーマの“仮説設計”
- 3.3. 行政に響く“言語設計”のスキル
- 4. アポ後の接点設計と“案件化までの育成フロー”
- 5. アポ代行を活用した企業の成功パターン
- 5.1. 誰に、どう届けるか」をアポ代行と共に設計している
- 5.2. 架電データを「単なる数値」ではなく、“営業の地図”として活用している
- 5.3. アポ代行を“外注”ではなく、“営業チームの一員”として扱っている
- 6. アポから成果へ。継続的に“動き続ける自治体営業”の設計図
- 6.1. 効果的なフォローアップの重要性
- 6.2. KPIの再設定:受注率から再接触率へ
- 6.3. 継続的な営業を支える仕組みづくり
- 7. まとめ
- 7.1. 成果が動き出すのは“アポ設計”から

目次
なぜ自治体営業は“アポが取れない”のか?
自治体営業において、もっとも大きなハードルのひとつが「担当者にたどり着けない」という接点構築の難しさです。
実際、商材や提案内容に自信があっても、「話を聞いてもらえない」「誰にアプローチすべきかすらわからない」といった壁にぶつかり、営業活動が停滞している企業は少なくありません。
これは単なる営業スキルの問題ではなく、自治体という組織構造と文化に起因する“制度的な難しさ”が背景にあります。
代表電話・部署経由では“担当者にたどり着けない”
自治体営業の最初の壁は、電話をかけても担当者に直接つながらないという構造です。多くの自治体では、代表電話から部署に転送されても、「現在担当者は席を外しています」「内容を伺って折り返します」といった対応で終わってしまうケースが多く、そのまま自然消滅することも少なくありません。
業務所掌の構造が複雑で、誰に届ければいいのかが不明瞭
民間企業と異なり、自治体の部署構成は縦割りかつ地域差が大きく、
たとえば「子育て支援」であっても、自治体によっては福祉課・健康課・こども未来課など、所管部署がまったく異なる場合があります。以下は、同じテーマで部署が分かれる一例です。
| 提案テーマ | 所管部署の例(自治体によって異なる) |
|---|---|
| 防災DX | 危機管理課・防災安全課・情報政策課など |
| 高齢者支援アプリ | 長寿支援課・高齢福祉課・地域包括支援推進室など |
| キャリア教育支援 | 教育総務課・生涯学習課・地域協働課など |
このように、誰に届けるかを見誤ると、最初のアプローチ自体が無効化されてしまいます。
異動が頻繁で、“人脈”が資産になりづらい
自治体では、人事異動が年に1回〜2回の頻度で実施されるため、
せっかくつながった担当者が次年度には異動し、再度ゼロからアプローチが必要になるというケースも日常的に発生します。
自治体営業では、“担当者の属人的なつながり”に頼った営業戦略は極めて脆弱であり、組織としての営業設計と、常に「新しい担当者とつながり続ける体制」が求められます。
営業を受け入れる文化が民間より防衛的
自治体の職員は、民間企業の営業担当者と比べて“営業を受け入れる”という文化が希薄です。これは、「特定企業との癒着を避ける」「公平性を保つ」「住民説明に支障をきたさない」といった行政倫理が背景にあるためであり、職員が慎重に対応せざるを得ない土壌があります。
その結果、営業電話に対しては以下のような心理が働きます。
「本当に必要かわからない話には関わりたくない」
「一度対応すると、継続的に連絡が来て負担になるのではないか」
「上司への説明が難しい話は極力避けたい」
つまり、民間の感覚で“提案すれば喜ばれる”と思ってアプローチしても、むしろ警戒される可能性が高いのです。
以上のように、自治体営業では「アポが取れない」のは特殊事情による構造的な課題であり、単純な営業リソースの問題ではありません。
だからこそ、“誰に、何を、どう届けるか”を自治体文脈に即して設計する戦略的アポ構築が不可欠です。次章では、多くの企業が陥りがちな「アポは取れたが案件化しない」営業の問題点について、具体的なパターンと改善の方向性を解説します。
アポを取れても「案件化しない営業」が陥る3つの落とし穴
自治体営業は、“つながった後”こそが勝負
テレアポによるアポ獲得に成功した――それは営業の第一関門を突破した証です。しかし、いざ商談に進んでも「検討だけで終わった」「提案を流された」「次につながらない」と悩む企業は後を絶ちません。
自治体営業において“案件化しない”という課題は、商談設計や接点の質に起因することがほとんどです。
ここでは、多くの企業が無意識に陥っている“3つの落とし穴”について、現場のリアルに即して解説します。
話す相手がズレている
所管外・キーマン不在では、どれだけ良い提案でも進まない
アポは取れたが、「それはうちの所管ではないので…」「別部署が担当かもしれません」と言われてしまう――これは自治体営業において最も多い失敗のひとつです。これは以下のような構造によるものです。
| よくある提案内容 | 実際の所管部署(自治体により異なる) |
|---|---|
| 中学生向けキャリア教育 | 学校教育課、生涯学習課、地域協働課など |
| 防災時の安否確認システム | 危機管理課、防災安全課、地域振興課など |
| 高齢者見守り支援サービス | 地域包括支援センター、高齢福祉課、福祉政策課など |
誰と話すかを誤るだけで、すべての提案が“的外れ”になってしまうのが自治体営業の難しさです。成功企業は、アポ前に業務所掌の調査・整理を行い、キーマンのポジションを予測したうえでアプローチしています。
トークや資料が“民間感覚”のまま:行政文脈への翻訳不足
次に多いのが、提案内容自体は良いのに、伝え方が自治体に合っていないという問題です。自治体は民間と異なり、営業に対して以下のような“行政特有の評価軸”で判断を下しています。
| 民間企業が重視する視点 | 自治代が重視する観点 |
|---|---|
| ROI(投資対効果) | 予算の根拠と責任説明 |
| スピード導入/即効性 | 業務の継続性・職員への負担軽減 |
| 導入による差別化 | 公平性・中立性(他自治体との整合性) |
| シンプルなコスト比較 | 議会で説明可能な価格設定 |
例えば「コスト削減に直結します」という表現も、自治体では「住民サービスの質を落とさずに運用可能です」と言い換えることで、行政としての文脈に沿った価値として受け止められやすくなります。
伝え方を“行政翻訳”することで、提案の納得性と通しやすさは格段に向上します。
フォローがなく“一回きり”:継続的な信頼構築が欠如している
― 自治体営業に必要なのは“訪問ではなく関係性の設計”
「一度訪問して資料を渡して終わり」――これでは、案件化はおろか、次のチャンスも生まれません。自治体では、導入検討に時間がかかるうえ、予算・議会対応・稟議など複数の関門があるため、継続的な接触が不可欠です。
成果を上げている企業は、以下のような“信頼の積み重ね”を営業フローに組み込んでいます。
| フォローアクション | 目的 |
|---|---|
| 導入実績・事例の定期提供 | 提案の再想起・温度感の再活性化 |
| 次年度予算化時期のリマインド | タイミングを外さすに再提案 |
| 異動時の新担当フォロー | 関係性を組織ベースで継続 |
| 定期的な情報提供メール | “営業されるている”ではなく“協力されている” 印象づくり |
自治体営業においては、「記憶に残る営業」より「記録に残る営業」が重要とも言われます。一回きりの接点で終わるのではなく、継続的に存在を思い出してもらえる仕組みが、案件化の可能性を広げるのです。
「アポが取れれば案件は動く」と思われがちですが、実際には“アポをどう活かすか”の設計ができていなければ、すべてが徒労に終わりかねません。
・話す相手を間違えないための所掌部署理解とキーマン特定
・民間ノリを避けた行政文脈への変換と資料設計
・一回きりで終わらせないフォローの設計と接点の継続
これらが備わって初めて、アポは案件化につながる“実働資産”となります。
成果につながる“自治体営業のアポ設計”とは
信頼され、動かすアポには「戦略の設計図」がある
アポが取れても、その後に何も進展しなければ、それは“アポ”ではなく“訪問許可”に過ぎません。自治体営業におけるアポは、提案や関係構築の「起点」であると同時に、今後の成約可否を左右する重要局面です。そして、そのアポの「質」は、事前にどこまで戦略的に設計できているかにかかっています。
この章では、成果を生む自治体アポを構成する3つの設計ポイントを、実践事例とともに詳しく解説します。
ターゲット部署と課題テーマの“仮説設計”
「誰に」届けるかを見誤れば、全てが無駄になる
自治体は、テーマごとに所管部署が異なるうえに、自治体ごとに組織構造も違います。「教育ICT」ひとつをとっても、ある自治体では教育総務課が、別の自治体では学校教育課や情報政策課が所管しているケースもあります。したがって、提案テーマと対象自治体の組織・施策・政策課題をもとに、どの課が意思決定のカギを握るかを“仮説立て”することが必須です。
▼ 実際の提案例:仮説設計の精度による違い
| 提案内容 | 成功したアポ設計 | 失敗したアポ設計 |
|---|---|---|
| 高齢者見守りサービス | 高齢者福祉課・地域包括支援センターに同時アプローチ | 市民課に提案⇨所管外で門前払い |
| 学校DX(クラウド教材) | 教務総務課・ICT支援担当と面談 | 生涯学習課に連絡⇨「学校対応ではない」と終了 |
| 避難所運営の業務支援アプリ | 危機管理課と事前に導入事例を共有 | 福祉課に打診⇨防災部門へたらいまわし |
このように、「誰に届けるか」が明確でなければ、どんなに優れた提案も届かないまま終わってしまいます。
行政に響く“言語設計”のスキル
アポで話す内容や、提出する資料の表現が民間企業向けのままでは、自治体には刺さりません。なぜなら自治体職員は、自分が話を聞いた提案内容を上司や議会、場合によっては住民に説明する役割も担っているからです。
つまり、提案内容がいくら素晴らしくても、「職員が庁内で再現できるトークかどうか」が問われているのです。
以下に、民間営業と自治体営業で使い分けるべき表現の一例を示します。
| 民間企業向けトーク | 自治体向けのトークへ変換 |
|---|---|
| 「業務効率化でコスト削減できます」 | 「住民サービスの質を維持したまま、財政健全化に貢献できます」 |
| 「ROIが高く、短期回収できます」 | 「導入効果を定期的に可視化し、議会説明にも活用できます」 |
| 「競合よりも安価で提案可能です」 | 「調達要件に沿った価格設定が可能で、入札対応実績もあります」 |
また、アポ段階から以下のような資料を持参・送付しておくと、案件化への動線が生まれやすくなります。
・他自治体での導入実績+担当者コメント
・導入による定量的な成果(住民満足度、稼働時間削減など)
・議会答弁や庁内稟議用の提案資料フォーマット
💡 ポイント:アポ時点から「この企業は行政対応をわかっている」と思わせると、職員の心理的ハードルが大きく下がります。
アポ後の接点設計と“案件化までの育成フロー”
自治体営業では、アポ後に案件化するまで1〜2年単位でかかることも珍しくありません。この期間を「待つ」だけでなく、「育てる」営業体制にしているかが、成果を分けるポイントです。
◆成果を出す企業が構築している接点設計フロー
①アポ獲得・初回ヒアリング
→ 担当部署の課題、予算枠、導入意向の有無を把握
②課題別に再提案/カスタマイズ資料を送付
→ 例:ヒアリングで得た「高齢者対応に注力中」という情報をもとに提案内容を最適化
③次年度予算要求時期に合わせて再アプローチ
→ 予算編成のタイミングに合わせて「再訪問の理由」を設計
④庁内調整資料・議会向け説明補助資料を提供
→ 職員の“説明負担”を下げる支援で、関係性が深化
⑤導入決定後の“顔が見えるサポート”体制で継続提案へ
このように、アポ後の関係性を戦略的に育てていく企業は、「タイミングが合えばまたお願いします」ではなく、「次に何をすべきか」を自ら設計して動かしています。
自治体営業は、民間とは異なる文脈とスピード感で動きます。だからこそ、「とりあえず会う」ではなく、“成果につながるアポ”を構造的に設計することが求められます。
・部署と課題テーマを踏まえた仮説設計
・行政の論理に翻訳されたトーク、資料の言語設計
・案件化までを見越した育成型フォロー体制の構築
これらを踏まえたアポ設計こそが、自治体営業の“成功法則”の本質であり、再現可能な成果をもたらす武器になります。
次章では、こうした営業設計を支援するテレアポ代行の実践例と、実際に成果を上げている企業の共通点について紹介します。
アポ代行を活用した企業の成功パターン
外注ではなく、“営業戦略の実装パートナー”としてのアポ代行活用
自治体営業において、「アポが取れない」だけでなく「営業の手が回らない」という課題を抱える企業は少なくありません。
自治体ごとに所管や課題が異なる中で、営業の属人化・再現性の欠如・対応リソースの不足といった問題は、営業活動のボトルネックとなりがちです。
こうした背景から、近年は自治体営業に強みを持つアポ代行(インサイドセールス)の活用が広がっています。
本章では、実際にアポ代行を活用して成果を出している企業に共通するパターンを、3つの視点で整理してご紹介します。
誰に、どう届けるか」をアポ代行と共に設計している
成果を出している企業は、アポ代行を単なる電話業務の外注先としてではなく、「営業設計の共創パートナー」として活用しています。
とくに自治体営業においては、「誰に話すべきか」「何をどの順序で伝えるべきか」の設計が命です。
| 成果が出ないパターン | 成果が出るパターン |
|---|---|
| 自治体一覧に無差別にアプローチ | 各自治体の組織構成をもとに、ターゲットを明確化 |
| 一律のトークスクリプトで架電 | 地域性や自治体ニーズに合わせた個別最適化リストを作成 |
| 営業部門と代行部門が分断されている | 営業戦略を共有し、アポ代行がチームの一員として並走 |
このように、「アポを取るため」ではなく、「アポから成果に導くため」に、アポ代行と連携して営業導線を組み立てているのが成功企業の共通点です。
架電データを「単なる数値」ではなく、“営業の地図”として活用している
アポ代行の強みは、「電話をかけてくれる」だけではありません。
日々の架電を通じて得られるリアルな自治体情報を、商談精度・再訪戦略・資料改善にまで活かすことで、営業成果は大きく変わります。
◆成果企業が重視する“架電ナレッジ”
| 取得情報列 | 具体的活用法 |
|---|---|
| 担当部署の温度感(前向き・保留・拒否) | 再提案やキャンペーン対象を絞り込み、無駄打ちを減らす |
| 所管課の違い・名称のばらつき | トークや資料の導入文を自治体名・部署ごとにチューニング |
| 予算タイミング・次回訪問可否 | 「半年後の訪問」のためのCRM入力と自動リマインド設定 |
アポ代行を“外注”ではなく、“営業チームの一員”として扱っている
成果を出している企業は、アポ代行を単なる委託先ではなく、社内営業部門と同じチームライン上に位置づけています。
◆実際の運用例
・月1回の定例MTGで案件化状況・トーク修正・自治体ニーズの最新情報を共有
・商談内容に基づいてトークを逆流改善(例:資料の切り口→冒頭トークへ反映)
・KPIは「アポ数」ではなく「再接触率」「担当者からの資料依頼率」など、信頼形成指標を重視
このような連携体制により、アポ代行は単に“電話をかける人”ではなく、自治体との関係構築フェーズを担う「初期接点の専門部隊」として機能しています。
自治体営業の肝は、「アポが取れたら終わり」ではなく、「信頼が始まり、案件が動き出すきっかけをいかに設計するか」です。そして、それを担う初期フェーズを“戦略的に実装する存在”がアポ代行なのです。
・誰に届けるべきかを共に設計し
・架電データを営業知見として蓄積し
・組織一体でPDCAを回す土壌を整える
これらを実現できている企業が、自治体営業で“提案が呼ばれる営業体制”を築いています。
アポから成果へ。継続的に“動き続ける自治体営業”の設計図
自治体営業において、アポイントメントの取得は単なる出発点に過ぎません。真の成果を上げるためには、アポ取得後の継続的なアプローチが不可欠です。この章では、持続的に成果を生む自治体営業の設計図を描きます。
効果的なフォローアップの重要性
アポイントメント後のフォローアップは、関係性を深め、信頼を築く上で欠かせません。具体的なアプローチとして、以下の方法が挙げられます。
・定期的な情報提供
自治体のニーズや関心に沿った最新情報や成功事例を共有し、継続的な関心を引きます。
・予算編成時期の再アプローチ
自治体の予算サイクルを把握し、適切なタイミングで再度提案を行います。
・イベントやセミナーへの招待
関連性の高いイベントに招待することで、対話の機会を増やし、関係性を強化します。
KPIの再設定:受注率から再接触率へ
成果を上げている企業は、KPI(重要業績評価指標)として「再接触率」を重視しています。これは、初回接触後にどれだけの頻度で再度コミュニケーションを取れるかを示す指標で、関係性の深さを測るものです。再接触率を高めることで、最終的な受注の可能性も向上します。
継続的な営業を支える仕組みづくり
持続的な営業活動を実現するためには、以下の仕組みが必要です。
・CRMシステムの活用
顧客情報やコミュニケーション履歴を一元管理し、適切なタイミングでのアプローチを可能にします。
・営業チーム内での情報共有
担当者間での情報共有を徹底し、チーム全体での戦略的な営業を推進します。
・アポ代行サービスとの連携
外部の専門サービスを活用し、アポイントメントの取得からフォローアップまでのプロセスを効率化します。
これらの仕組みを整えることで、継続的かつ効果的な自治体営業が実現できます。
まとめ
成果が動き出すのは“アポ設計”から
自治体営業は、提案力だけでは成果に結びつきません。
本当に重要なのは、「誰に・いつ・何を・どう届けるか」を設計した戦略的なアポ設計です。
私たちタノメイトは、自治体営業に強みを持つアポ代行として、成果につながる初期接点の構築と継続支援を行っています。
▶︎「つながる」だけでなく、「動かす」営業へ。まずはお気軽にご相談ください。
👉 自治体営業に強いアポ代行サービス「タノメイト」

タノメイト編集部です。テレアポのプロの視点から、テレアポに関するさまざまな情報をわかりやすく発信します。
【タノメイトとは?】
タノメイトは「質の高いリード獲得」にこだわる、成果報酬型テレアポ代行サービスです。リード獲得にお悩みの企業様はぜひお問い合わせください。
商談につながるアポを獲得
完全成果報酬型テレアポ代行
『タノメイト』
● 初期費用・固定費0円
リードを獲得した分だけお支払い。完全成果報酬型でリスクゼロだから今すぐ始められます。
● 質の高いリード獲得
成功事例に基づくスクリプトと精度の高いリストを活用。質の高いリードを獲得します。
● 安心のキャンセル保証
条件をクリアしたリードのみご案内。条件を満たさないリードはキャンセル可能です。

\ リスクゼロで始めるテレアポ代行 /